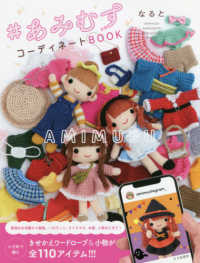出版社内容情報
福岡市が地方最強都市と言われるのはなぜか。著者の徹底取材によって明らかとなる、福岡市の都市競争力と地方が生き残るためのヒント!
木下斉[キノシタヒトシ]
著・文・その他
内容説明
まちづくりとはどこかの「真似をする」のではなく、これまでの「常識を疑う」ことである。「常識破り」の戦略がまちを強くする。
目次
第1章 まちづくりは「常識」を疑え!
第2章 福岡市は「ここ」がすごい!
第3章 福岡市5つの「常識破り」
第4章 福岡市を変えた10の「覚悟」
第5章 経営視点で見える「福岡メソッド」
第6章 福岡市の「制約」と「未来」
著者等紹介
木下斉[キノシタヒトシ]
まちビジネス事業家。一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事。一般社団法人公民連携事業機構理事。1982年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。経営学修士。高校在学中に早稲田商店会の活動に参画、出資会社の社長に就任。大学院在学中に経済産業研究所、東京財団などで地域政策系の調査研究に従事。2009年、一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンスを設立、代表理事就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
99
木下さんの本は他に読んだことがある。「東京任せではいけない」・「官ではなく民が主導で」・「都市ではなく都市圏で」・「金がなければ知恵を出せ」・「補助金・助成金はあてにするな」。これらの考え方に沿ってちょうど良い感じで紹介できる都市が福岡市だったという印象を受けた。販売するための本だからといえばそれまでだが、よくぞここまで調べてくるなと感心した。巻末の参考文献がその洞察や観察眼の鋭さに箔を付けている。このボリュームでまちづくり事業に取り組む人にとって1,600円は安いのではないだろうか。2018/07/08
ミライ
36
「福岡が伸びている」というニュースは最近いろいろと聞くのだが、「なぜ成功しているか?」の疑問は常々感じていたので、表題をみた瞬間に即購入。中身は福岡市が日本の各都市と比べて「なぜ」発展したのかをわかりやすく解説されていて非常におもしろかった。中でも明太子の話が興味深く、開発元のふくやが製法をオープンソースにして公開したあたり、当時では(ネット時代の今となってはあたりまえだが)すごいことだったんだなと思う。他と同じことをしていたら停滞するし進化もないということは、すべてに共通した考えだと再考させられた。 2018/03/03
Kentaro
35
天神の西隣にある大名や、JR博多駅周辺にIT関連産業の拠点が集積。レベルファイブは従業員300人を擁し、LINEがサービス開発拠点として設立したLINE Fukuokaもすでに900人を超える社員を抱えるまでになっている。このような企業群の集積が呼び水となり、新たなクリエイティブ・イノベーション関連企業が福岡に拠点を設立するという好循環を生み出している。福岡市は、もともと博多の商人によって経済が栄えた歴史のためか、「まちづくりは、あくまで民間が主体。行政はできる範囲のサポートに回るのが鉄則」と力説する。2019/10/30
サトシ@朝練ファイト
30
アジア各国の人口ボーナス期なんてのも考慮に入れてるんだ。2018/05/20
ケー
28
大学生の時に住んで以来の福岡市信者としては読まざるを得ない一冊。昔は貿易の長崎市、佐世保市、行政の熊本市、鉄鋼業の北九州市など名だたる都市に囲まれていた福岡市。時には渇水も起こるほど都市基盤の脆弱な土地でもあった。では何故九州の中核都市として君臨したのか⁉︎その理由を歴史、地理、人物、気質から読み解く。制約の多い環境だからこそ創意工夫で成長したというのは納得。二次産業がないからこその三次産業に注力し、それが今、開花している。また、福岡市だけで自己完結せず周辺自治体を巻き込む「都市圏思想」は目からウロコ。2018/02/27