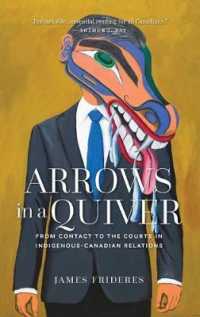出版社内容情報
東京は地方以上に急激な高齢化に襲われる。インフラ維持が困難になり、既に低下している国際競争力はさらに落ちる。対応策を考える。
【著者紹介】
政策研究大学院大学名誉教授
内容説明
地方の集落の消滅を危惧する声が高まっているが、むしろ、地方よりも東京のほうがより急激な変化に見舞われると考えられる。東京の高齢化はすさまじい。2040年には、2010年に比べて高齢者が143.8万人増加する。その結果東京の貯蓄率は低下し、インフラが維持できず、都市がスラム化するおそれがある。多くの高齢者が家を失い、老人ホームも圧倒的に不足する…。ならばどうするか。欧州の事例も参考にしながら現実的な対応策を提案する。
目次
序章(国のタブーその1―少子化対策;国のタブーその2―経済成長の追及 ほか)
第1章 東京これからの現実(東京では高齢者が三〇年間で一四三・八万人増える;貧しくなる東京 ほか)
第2章 東京劣化現象への誤解(東京の現在の人口構成は維持できない;出生率二・〇七は絶対に達成できない―未婚率に注目すべき ほか)
第3章 これからの東京の経済(日本経済を支えたビジネスモデルの終焉;不可解な設備投資を続ける日本企業 ほか)
第4章 なぜ政府は間違えるのか―人口政策の歴史が教えてくれること(人口政策がいびつな人口構造を生み出した;「産めよ殖やせよ」が急速な人口減少の主因 ほか)
第5章 東京劣化への対処 今できること(増税では到底解決できない財政赤字の大きさ;「一人当たり租税収入」と「一人当たり財政支出」で予算編成を ほか)
著者等紹介
松谷明彦[マツタニアキヒコ]
政策研究大学院大学名誉教授、国際都市研究学院理事長、工学博士(東京大学)。1945年、疎開先の鳥取県で生まれる。東京大学経済学部経済学科、同学部経営学科卒業。大蔵省主計局調査課長、主計局主計官、大臣官房審議官等を歴任。1997年、政策研究大学院大学教授に就任。2010年国際都市研究学院を創設。2011年名誉教授。専門は、マクロ経済学、社会基盤学、財政学。人口減少研究における日本の第一人者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
いたろう
Miyoshi Hirotaka
1.3manen
ふろんた2.0
-
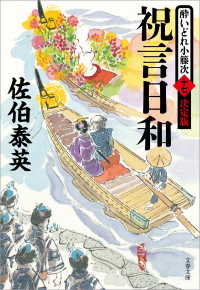
- 電子書籍
- 祝言日和 酔いどれ小籐次(十七)決定版…
-

- 電子書籍
- 血海のノア WEBコミックガンマ連載版…