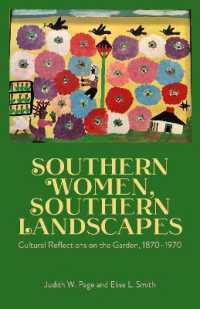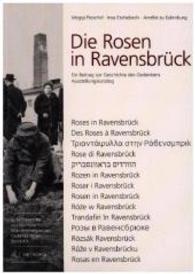出版社内容情報
ごみをへらすために、また、限られた資源を有効活用するために、原材料や設計まで視野に入れたリサイクルの技術が日々進歩しています。本書では、マテリアル、ケミカル、サーマルなどのリサイクルの種類や、社会の変化とリサイクル関連の法律を紹介するとともに、身近なモノのリサイクルの方法と技術、リサイクル率などの現状をわかりやすく解説します。
[第1章]ごみとリサイクル……「ごみ」って何?/ごみの処理の方法/ごみをへらすために/リサイクルをすすめる工夫/リサイクルの種類/環境にやさしいリサイクル/社会の変化とリサイクルの法律/コラム:ごみを燃やすとどうなるの? [第2章]どうしてる? 身近なもののリサイクル……アルミ缶とスチール缶/びん/プラスチック/ペットボトル/食品/紙/衣類/電池/蛍光灯/コラム:世界のごみ処理とリサイクル/家電/小型家電/自動車/建物/コラム:太陽光パネルのリサイクル
田崎 智宏[タサキ トモヒロ]
監修
目次
1章 ごみとリサイクル(ごみって何?;ごみの処理の方法;ごみをへらすために;リサイクルをすすめる工夫;リサイクルの種類 ほか)
2章 どうしてる?身近なもののリサイクル(アルミ缶とスチール缶のリサイクル;びんのリサイクル;プラスチックのリサイクル;プラスチックのリサイクル ペットボトル;食品のリサイクル ほか)
著者等紹介
田崎智宏[タサキトモヒロ]
国立環境研究所で資源循環・廃棄物研究センターの循環型社会システム研究室長を務める。リサイクル問題・ごみ問題を研究しつつ、持続可能な社会を目指す研究に取り組んできた。システム工学と環境政策学が専門で、家電や容器包装などのリサイクル制度やごみ発生抑制・長期使用の取り組みの評価、リサイクルの責任論としての拡大生産者責任の研究などについて学問領域を超えたアプローチで研究を行う。博士(学術)。中央環境審議会などの委員も務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
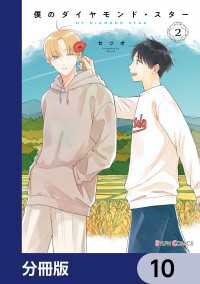
- 電子書籍
- 僕のダイヤモンド・スター【分冊版】 1…
-

- 電子書籍
- きみに恋する殺人鬼【単話】(20) マ…