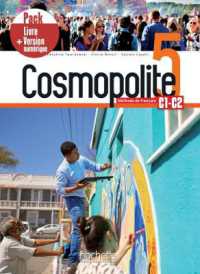出版社内容情報
人生に活かせる「論語」の智恵をやさしく解説。
京大総長として、医師として、世人の敬愛を集めた著者が、『論語』を通して己れを見つめ、意義ある人生を送るための叡智を説き明かす。
生き方の指針として、広く世に知られている『論語』。孔子とその弟子達の言行を集録した「東洋最大の古典」は、味わい深い人生を過ごすための知恵を私たちに授けてくれる。しかし一方で、堅苦しい、難しいというイメージを持っている人が多いことも事実だ。
▼本書は、医師として、京大総長として、世人の敬愛を集めた著者が、私たちの生活に関係が深い言葉を『論語』から20選び、自身の体験を通しながら、やさしい言葉で価値ある人生を送るための叡智を説き明かしたものである。
▼例えば、「過ぎたるは猶ほ及ばざるがごとし」とは、やり過ぎるのも、やり足らないのも感心できないということである。著者は、そのような私達自身が持っている欠点を自覚し、改めてこそ、人間としての成長と学問をする真の意義がある、と解説している。
▼目先の利害や得失にとらわれることなく、人として生きる上で、本当に大切なものは何かを教えてくれる、心に響く講話集である。
●学びて時に之を習ふ
[学而第一]
●三人行へば
[述而第七]
●歳寒くして
[子罕第九]
●我れを知る莫きかな
[憲問第十四]
●博く文を学びて
[雍也第六]
●耳順ふ
[為政第二] ほか
内容説明
「過ぎたるは猶ほ及ばざるがごとし」とは、やり過ぎるのも、やり足らないのも感心できないということですが、本当の意味は、そのような性格を自覚し、改めてこそ、真の学問の意義があるということです―本書は、医師として、京大総長として、世人の敬愛を集めた著者が、『論語』から私たちの生活に関係が深い言葉を20選び、価値ある人生を送るための叡智を語り明かした心に響く講話集である。
目次
学びて時に之を習ふ(学而第一)
三人行へば(述而第七)
歳寒くして(子罕第九)
我れを知る莫きかな(憲問第十四)
博く文を学びて(雍也第六)
耳順ふ(為政第二)
耳順ふと耳悦ぶ(為政第二)
人を以て言を廃せず(衛霊公第十五)
君子に三畏あり(季子第十六)
匹夫も志を奪ふべからざるなり(子罕第九)〔ほか〕
著者等紹介
平沢興[ヒラサワコウ]
明治33年、新潟県に生まれる。大正13年、京都大学医学部卒業、同大学解剖学教室助手、助教授、新潟医科大学助教授、この間2年半欧米に留学。昭和5年、新潟医科大学教授。昭和21年、京都大学教授、教養部長、医学部長を歴任。昭和26年、錐体外路系の研究で日本学士院賞を受賞。昭和32年、京都大学総長。昭和38年、総長を退任、名誉教授。昭和42年、日本学士院会員。昭和45年、勲一等瑞宝章受章。昭和47年、新学社総裁。昭和60年、関西師友協会顧問。平成元年6月17日、逝去
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ダイキ
かんたろう
きくちたかし
-
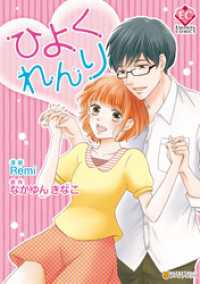
- 電子書籍
- ひよくれんり エタニティCOMICS