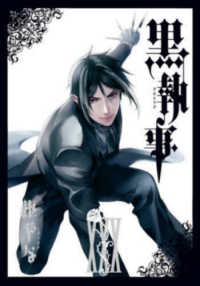出版社内容情報
家族で「ある」ことから、家族を「する」へ。
子育てを拒否する母親、母親の役目を担う父親。家族で「ある」ことから家族を「する」ことが、現代家族の病理を救う。渾身の書き下ろし。
子育て、家事もしながら一生懸命働こうとするスーパーウーマン。現代は、母親であることが難しい時代だと著者は言う。巷には「母性崩壊」「幼児虐待」という言葉がにぎわっている。しかし、母親を責めるばかりではなく、時代に適した家族のつくり方が必要だと主張する。
▼そこで求められるのは「マザー・ファーザー」としての父親だと言う。「マザー・ファーザー」とは、文字通り母親の役目も担う父親像のことである。
▼それと同時に著者は「家族である(ビーイング・ファミリー)」から「家族する(ドゥーイング・ファミリー)」ことが大事だという。血縁関係である家族の形態が崩壊しつつある今、遠距離で暮らす家族の成員同士が点と点で結びつき、携帯電話やインターネットのようにネットワークで結びつく必要があるともいう。お互いに家族であることを意識し、家族をつくっていくことがこれからの家族を救う唯一の家族改革の道筋なのである。家族に悩む人必読!
[第1部]変化する家族にどう対応するか
●第1章 「母親である」ことがむずかしい時代
●第2章 夫婦関係を取り戻す新しい愛のあり方
●第3章 子どもの心は変わってしまったのか
●第4章 変わる社会の中でひきこもる若者たち
[第2部]「家族である」から「家族する」時代へ
●第5章 愛をどう取り戻すか
●第6章 高齢社会の家族と個人の生き方を考える
●第7章 死を考えることで生をみつめる
●第8章 「マザー・ファーザー」する父親
●第9章 意識的に「家族する」ことが鍵になる
内容説明
威厳ある父親、子育て上手の母親になれなくても大丈夫。スーパー・ウーマンとマザー・ファーザーがつくる新しい家庭。
目次
第1部 変化する家族にどう対応するか(「母親である」ことがむずかしい時代;夫婦関係を取り戻す新しい愛のあり方;子どもの心は変わってしまったのか;変わる社会の中でひきこもる若者たち)
第2部 「家族である」から「家族する」時代へ(愛をどう取り戻すか;高齢社会の家族と個人の生き方を考える;死を考えることで生をみつめる;「マザー・ファーザー」する父親;意識的に「家族する」ことが鍵になる)
著者等紹介
小此木啓吾[オコノギケイゴ]
精神科医。1930年東京都生まれ。慶応義塾大学医学部精神医学科卒。同大医学部教授を経て、現在は東京国際大学大学院臨床心理学研究科教授、慶応義塾大学環境情報学部客員教授など。1977年、『中央公論』誌上に載せた「モラトリアム人間の時代」によって、一躍有名になる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- サンデー毎日2022年9/18号