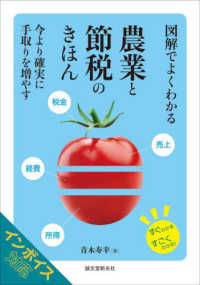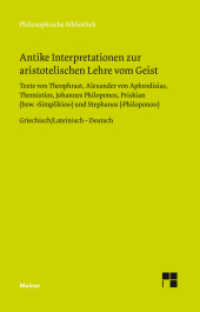出版社内容情報
【著者からのコメント】
“ブーム”といっては不謹慎かもしれませんが、近年、評論の世界では異分野の方々による教育再建論が目立ちます。かくいう私も、憲法学を専攻している人間です。「なぜ、教育の専門家でもないオマエのような人間が教育を論じるのだ」と問われれば、私は反問したい。「では、教育の専門家である教育学者や文部官僚が推進している『教育』をあなたは支持できるのですか。その実態をご存じですか」と。
「ゆとり」「生きる力」「平等」「個性重視」「人権」……。いずれも、俗耳に入りやすい麗しい言葉です。教育学者や文部官僚は、これらの言葉を教育のキーワードとして多用します。では、それがどのような形で学校現場で体現されつつあるか。
テストや競争の廃止、生徒を注意できない教師、校則の解体、「被差別の視点に立つ」同和教育の導入等々、その実態を知れば、親は驚きと不安を禁じえないはずです。かつてであれば、わが子の教育に対して、父親が無関心でも母親がしっかりと見守っていたのでしょうが、近年は共働き夫婦が増加したためか、「教育は学校まかせ」というご家庭が少なくない。それが、学校による子供の私物化をますます進める。本書でも詳述しましたが、いまだに教職員組合の組織力が強い広島、三重、大阪などでは、親が聞けば愕然とするであろう偏向教育が罷り通っています。これは一種のマインド・コントロールといってもいい。
では、教育の最後の砦ともいうべき「家庭」は安泰かといえば、ここでもまた、「多様な家族」「個の自立」「ジェンダー・フリー」「男女共同参画」といった美辞麗句とともに、家族破壊が行われようとしている。またぞろ「夫婦別姓」を法制化しようとする動きが一部にありますが、私たちは彼らの目的、思想をよく見極める必要があると思います。そして、想像してみてください。それがどのような社会を招来するかを。
悪しき人権思想・平等主義から学校を救え!
日本の教育荒廃は、なぜ、誰によって引き起こされたのか。日本の教育、家族を保守するために論戦を挑み続ける若き論客の最新評論集。
教育評論家でも教育学者でもなく、憲法学者である著者が教育問題を論じることを訝る向きもあろう。だが、それは筋違いなことではない。
▼戦後教育の理念を示したものに現行の教育基本法があるが、その前文は「この(日本国憲法の)理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」と謳っている。果たして今日、日本国憲法の理想を体現した人格を育成することを目的とした戦後教育はいかなる姿となって立ち現れているか。いうまでもなく、教育荒廃である。
▼今日の教育荒廃が、道徳教育を放棄した一方で「個人の尊厳」「人権尊重」などの空念仏を唱えてきた戦後教育という壮大な実験の所産であることは論をまたない。私たちはいま、教育荒廃という大きな犠牲を払って日本国憲法の理念の不当性を見せつけられている。
▼近代憲法学の理論的帰結としての「行き過ぎた個人主義」に疑念を呈し、日本の教育、家族を保守するための論を展開する著者の最新評論集。
●第1章 文部行政に異議あり!
●第2章 戦後教育の呪縛
●第3章 家族を破壊する「ジェンダー・フリー」
●第4章 偏向教育の現場から
内容説明
「ゆとり教育」や個性尊重教育など文部行政への批判、戦後教育法制の問題点の剔抉、行き過ぎた人権教育や同和教育などによる偏向教育の告発など、多岐にわたる、著者の第二評論集。
目次
第1章 文部行政に異議あり!(臨教審の「個性重視」路線を見直す時;今こそ「基本に返れ!」 ほか)
第2章 戦後教育の呪縛(「人権」の基礎として道徳教育が必要;教育正常化に逆行する人権教育・啓発推進法 ほか)
第3章 家族を破壊する「ジェンダー・フリー」(家族の絆なくして「個人」なし;フェミニズムに悪用される少子化対策 ほか)
第4章 偏向教育の現場から(公教育への“監視”が必要な時代;校長よ、一歩前へ! ほか)
著者等紹介
八木秀次[ヤギヒデツグ]
1962年広島県生まれ。早稲田大学法学部卒業。同大学院政治学研究科博士課程中退。専攻は憲法学・思想史。現在、高崎経済大学助教授。いま、論壇で最も注目されている若手論客で、“保守主義”の立場から斬り込む論考には定評がある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 芸能人式ダイエット