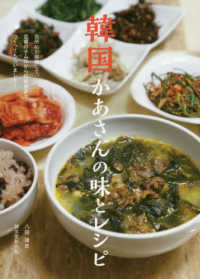出版社内容情報
話材豊富な人生をつくるための必携の一冊。 知っているようで知らない話、あまりに意外でビックリな話……世の中は、オモシロイ話でいっぱい! 話材豊富な人になるための必携の一冊。 ビタミンCの味ってどんな味? 草花の茎はどうして円柱形になっているの? 時刻表にも載っていない駅があるって本当? スカンクは自分が放った悪臭には何ともないのだろうか? 電子レンジで温めたものは、なぜか冷めやすい? などなど、身の回りには知っていそうで知らないこと、「なぜ?」「ホント?」と思うようなことが少なくない。こうしたことの答えや理由を人が集まったときなどに披露すると、その場が盛り上がることは確実。 本書は、みんなが知っていそうだが、案外知られていないこと、普段は気にも留めないが、改めて問われると答えに窮してしまうことなど、思わず人が感心してしまうような恰好の“話のネタ”を、歴史や科学、ことば、動物、植物、食べ物、からだなど幅広いジャンルから一日一話形式で取り上げた雑学読本である。 どのページから読み始めても知らず知らずのうちにおもしろ知識が身についていく、とっておきの話のネタ366篇。 ●ニシンの子を「数の子」と呼ぶのはなぜ? ●ハエは足にも舌を持っている ●アメリカ国家はイギリスの借りもの!? ●ピアノの鍵盤はどうして白と黒なのか ●日本の切手に初めて登場した外人は? ●江戸時代にも“ピル”があった!? ●郵便番号の順番はなぜ不ぞろいなのか ●本邦ミネラル・ウォーター事始め ●日本の中にある「日本国」とは? ●利息を決めずに金を貸したら…… ●紙で作った餅??江戸時代の珍奇な食物 ●臍の緒を大切にする習慣は日本だけ?
内容説明
ビタミンCの味ってどんな味?草花の茎はどうして円柱形になっているの?時刻表に載っていない駅がある?スカンクは自分が放った悪臭には何ともないのか?電子レンジで温めたものはなぜ冷めやすいのか?フィルムの枚数はなぜ12の倍数なのか?歴史や科学、ことば、動物、植物、食べ物、からだ…、読んだぶんだけおもしろ知識が身についていく、とっておきの話のネタ366篇。
目次
1月の章(ニシンの子を「数の子」と呼ぶのはなぜ?;有馬温泉にはかつて馬がいたのか ほか)
2月の章(ハエは足にも舌を持っている;天台宗では「和尚」が「かしょう」 ほか)
3月の章(アメリカ国歌はイギリスの借りもの!?;“助産婦”が出産を助ける動物とは? ほか)
4月の章(ピアノの鍵盤はどうして白と黒なのか;アメリカ人は“スキンシップ”をしない!? ほか)
5月の章(日本の切手に初めて登場した外国人は?;体脂肪計に乗るだけで測定ができるわけ ほか)
6月の章(江戸時代にも“ピル”があった!?;昔の力士は“化粧まわし”で相撲をとった ほか)
7月の章(郵便番号の順番はなぜ不ぞろいなのか;卵を丸のみしたヘビが殻を割る法 ほか)
8月の章(本邦ミネラル・ウォーター事始め;角帽のそもそもの目的とは? ほか)
9月の章(日本の中にある「日本国」とは?;なぜ神輿は揺すったりするのか ほか)
10月の章(利息を決めずに金を貸したら…;なぜ早食いは肥満のもとなのか ほか)
11月の章(紙で作った餅―江戸時代の珍奇な食物;紫はどうして高貴な色になったのか ほか)
12月の章(臍の緒を大切にする習慣は日本だけ?;猫は落ちるのが上手!? ほか)
-

- DVD
- 未来よこんにちは