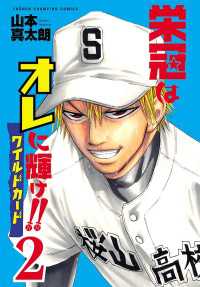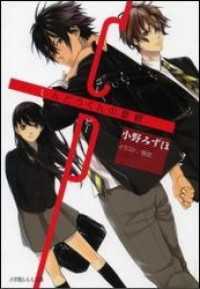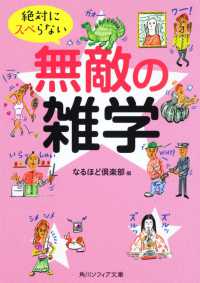出版社内容情報
アダム・スミス、マルクス、ケインズという経済学三巨人の思想を再検証。新しい「豊かさ」のために経済学はどうすべきかを問い直す。
内容説明
経済学が資本主義を「飼い慣らす」ことを試みた二百年間は、ムダだったのではないか?金儲けという「狂気」が、我々を熾烈な競争に駆りたて、人間が生きるために貴重な多くのものを破壊する―結局、そんな「無理」の上にしか存在しえない「豊かさ」を、経済学は模索してきたのか?経済学者としての自省をこめて、アダム・スミス、マルクス、ケインズという三巨人の思想を再検証する著者が、前著『日本の反省』に続いて、さらに深く「豊かさ」の意味を問う、社会哲学の書。
目次
序章 愚かな過ち
第1章 経済成長の幻想
第2章 「豊かさ」の正体
第3章 「見えざる手」の神話―アダム・スミスの命題
第4章 資本主義の「狂気」―カール・マルクスの命題
第5章 「福祉国家」の栄光と悲惨―ケインズの命題
第6章 経済学を超えて
終章 人間とは何か
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
90
現実の(1997年当時)経済をもとにして、経済学史的な観点から日本の今後の行く道を模索しているのでしょうが、やや論点が弱い感じがいました。飯田先生の言っていることはもっともなのですが、マルクスや、スミス、ケインズを持ち出して論じていく必要があったのかは若干疑問の残るところです。日本現実の経済を分析して論破してくれたらと感じました。昔のキレが少し鈍くなった気がします。2016/01/17
Humbaba
9
資本主義の歴史は200年にも上り,その間様々な経済学者が経済学を発展させるために議論を深めてきた.物質的な観点でのみ考えれば,かつてと比べて手に入る物は増えた.しかし,では我々はかつてよりも豊な暮らしを享受できているのだろうか.2013/03/16
ひゃくめ
4
経済学の入門に最適。だけど入門なのに「終わる」哀しさ!1997年新自由主義的な規制緩和が叫ばれてる頃の本。それを真っ向否定しているのは、あの頃だとかなり珍しい?その後誕生した小泉竹中がやらかした事を考えると、ほんとテレビ新聞は腐ってるなと。飯田氏は正しかった。ひとつ発見したのはアダムスミスは性善説で国富論を書いたこと。合理的人間モデルで書かれる近径とはちと違う。不気味なのは日本人の多数が新自由主義、莫大なアメリカ国債の買い入れ、レーガン貿易摩擦問題、の真の姿を知らされていない事。飯田氏の本はやはり良い。2012/12/17
Humbaba
1
物事を理解するためにはそれなりの理論が必要である。実態がつかみにくいものだからこそ理論を大切にすることは間違っていない。しかし、理論だけが先行したところで、それが実態と合っていなければ価値は薄れていく。条件が変われば今まで使えた理論が使えなくなるのは仕方がない。しかし、変わり続けるものに追いつけなければ無用のものでしか無い。2016/01/08
風見じじい
1
バブル崩壊後5年ほど経った頃の本です。アダムスミス、マルクス、ケインズという経済学の3人を取り上げ、新古典主義経済学者が言っていた「規制緩和」は資本主義に内在する狂気に気づいていなかった頃のアダムスミスの経済学に逆戻りするのではないかという恐れから、本書は書かれています。大仰な題名からは真意が伝わりませんが、「経済学の行き詰まり」程度の意です。経済学史の基本を知るのには良い本だと思います。 ケインズの有効需要の創出は失業と飢えの恐怖から解放するが政府へのタカリであり財政赤字を生むと言っています。2012/10/10