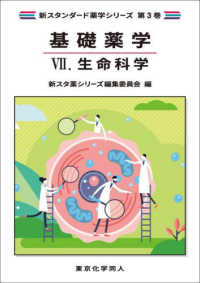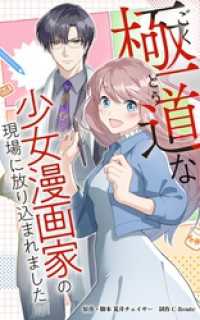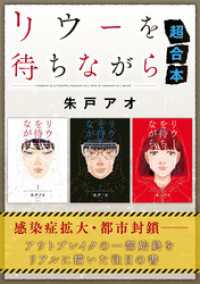目次
染色は白に始まる
大国主命の御衣の色
古代から伝えられた泥染の黒
南方より渡来した民族がもってきた青
紀元前に大陸より渡来した茜草
卑弥呼の色
紫草はどこにでも自生していた
貝紫は縄文時代に染めていた
古代の五色
庶民の服色の黄、黄蘗など〔ほか〕
著者等紹介
山崎青樹[ヤマザキセイジュ]
1923年東京市渋谷区中渋谷に生まれる。1946年長野県南佐久郡前山村に父・斌(あきら)とともに月明手工芸指導所を設け、草木染研究所を併設する。1956年群馬県高崎市に草木染研究所を移す。1975年労働大臣より卓越技能者賞を受ける。1977年群馬県重要無形文化財に指定される。1978年群馬県文化功労賞を受ける。1982年民族衣裳文化普及協会より、きもの文化賞を受ける。1983年黄綬褒章を受ける。1986年日本画院幹事。1987年高崎市文化賞を受ける。1992年群馬県功労者として表彰される。1994年高崎市染料植物園開園に関与する。1995年フランス・ツールーズで開催された国際インジゴ会議で「若葉による緑色染」を講演し、作品を展示する
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
10
図書館本。正倉院から古代の美繋がりで染色について読んでみた。縄文時代に貝紫などの染色があったかもしれないらしい。草木から作られる素晴らしい色の数々。煎汁を何回も煮出し、何度も漬ける手間のかかる物だ。アルカリ性や酸性など、色によって媒染を使い分けるなんて、誰が最初に思いついたのか?当時はPHなど分からなかったのにどうやって?材料の樹皮にも染料として採集に最適な時期があるらしい。原料の草木と出来上がりの色もカラー写真でつけて欲しかった。現在は酢酸アルミや過酸化水素水を使うという色は当時は何を使っていたのかな?2018/11/08