目次
「ひと」への進化
ホモサピエンスの移動と人種の形成
氷河時代人の思想
新石器時代人の思想
古代文明の世界
カナンとイスラエル
森林のインド
判断中止
草原と森林の中国
「肉体をとりて生まれ」
大乗仏教と上座部(小乗)仏教
砂漠のイスラム
仏教の東進
キリスト教の拡大
結論
著者等紹介
鈴木秀夫[スズキヒデオ]
1932年神奈川県に生れる。1955年東京大学理学部卒。現在、清泉女子大学教授。東京大学名誉教授。理学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
105
久しぶりの再読です。40年以上前に読んだのですが、和辻哲郎の「風土」との比較で読んだ覚えがあります。人類の起源などについても書かれていて風土とそれに伴う宗教についても論じられています。どちらかというと哲学的な和辻よりもこの本はフィールドリサーチ的な観点であると感じます。薄いけれども内容は結構深いものがあり興味深いものです。2017/10/23
デビっちん
23
再読。モンゴロイド、ネグロイド等々、私たちの体が風土によって形作られていることは周知の事実であると思います。しかし、体だけでなく、思考までもが風土によっていたのです。目に見える体と違い、頭の中を覗くことができないということによって、理解は困難になるからです。つまり、人間はその生まれ育つところの環境の影響から脱し切ることはできないということが言えます。ここから、何か変化を起こしたいと考えたときは、住む場所を変えるのが1つの手になるんだと思いました。本も読む場所によって、受け取り方が違うのかなとも感じました。2017/04/19
澄
9
森林の思想、砂漠の思想を根底に各宗教を説く。仏教の章のなかで日本の項があるのだが、そのなかで「…日本は、その最良の部分のみを持っているわけで、一国単位でみれば、地上、再恵の国ということができると思う。ところが、われわれは、そのことをあまり明確に理解していない。かえって、日本を自然災害の多い国として意識している。」と説いている内容に日本は自然条件もいい国、住みやすい国であると再認識させられた。2018/06/30
デビっちん
6
人間の歴史は、超越者の声を聴こうとする歴史である。人間はその生まれ育つところの環境の影響から脱し切ることはできない。人は、同じものを食べる人同志との結びつきを強くするが、反対に、食べ物の異なる人は排斥する習性がある。風土から生物体としての身体が形づくられるだけでなく、思考もが形勢された。風土と文化の関係から、宗教の発明までを説明さている。乾燥の土地が唯一神のより早い理解に貢献し、湿潤の土地は、判断中止という思想の深みに達する貢献をなした。あの発言の裏を推察する際に、風土という視点を取り入れてみる。2015/05/29
dexter4620
1
さすがの鈴木秀夫氏。小難しく書くことに長けているが、気候や風土が宗教の分布に影響している事は何となく理解できた。2021/10/22
-
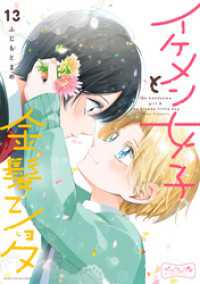
- 電子書籍
- イケメン女子と金髪ショタ ベツフレプチ…
-

- 電子書籍
- ソフトウェア品質知識体系ガイド (第3…




