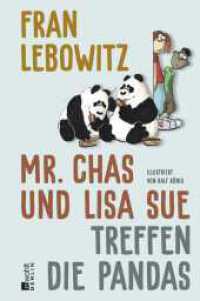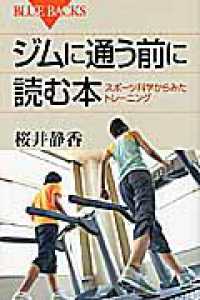出版社内容情報
観光学の大家による、ユニークな視点で書かれた日本の地域論。うたわれる地域には魅力があるという、地方の魅力変遷に関する分析は、政治、経済、社会状況の鋭い洞察をふくみ、単なる懐古談にとどまらない深い内容となっている。
内容説明
明治時代の童謡・唱歌から平成ご当地ソングの女王までの100年から、日本の街の変遷をたどる。
目次
序章 ご当地ソングの魅力と威力
第1章 魅力あるまち、日本列島うたの地図
第2章 ひとの集うあこがれのまち、うたのまち
第3章 うたによる文化おこし、まちおこし
第4章 ご当地ソングにひそむ果たせぬ心情
補論 日本の「うた」の定義、資料、時代区分
著者等紹介
溝尾良隆[ミゾオヨシタカ]
昭和16年(1941年)生まれ。観光学者、理学博士。地域観光学および観光地理学を専門とする。東京教育大学理学部地学科地理学専攻卒業後、財団法人日本交通公社主席研究員、立教大学観光学部教授、同学部長、城西国際大学観光学部教授を経て、現在、帝京大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
qoop
3
特定地域を唄った唱歌や歌謡曲の歌詞からその地域を想起させる文言を抜き出し、時代によって地域イメージに変化があるかどうかを探るというのは面白い(が、その点に関してはアイディア先行だったようにも思う)。歌のイメージに沿って地域が後追いで街作りを進める例など興味深いものもあるが、現状しりすぼみのご当地ソングが復権することはあるのだろうか。例えば鬼”小名浜”のような地域性を核としたラップなど、著者はどう扱っただろうか。ご当地ソングの枠を広げる存在か、それとも十分枠内にあると見たろうか。2015/08/12
Kiyoshi Ohshima
2
暮らした街には、やはりうたを通じて思い入れができる。2015/07/23
海
2
この本の一番残念な点は、歌詞に著作権があるから載せられないので、著作権切れ、もしくは不明のものだけしか歌詞が載せられなかったところだと思う。歌の内容を説明してもらっても、知らない曲はやはりピンとこない。「歌で町おこし」については今の団塊世代以上が好きそうなイベントばかり羅列してあったけど、今の若い人達のロックフェスなんてその部類に入るんじゃないかな、と思った。2012/03/11
-

- 電子書籍
- 直売所、行ってきます Nemuki+コ…
-
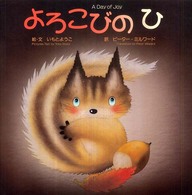
- 和書
- よろこびのひ