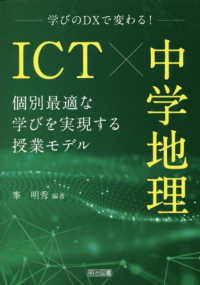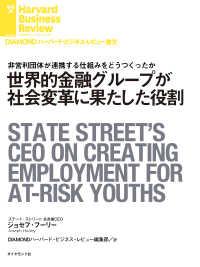出版社内容情報
共通の課題を持ちながら、理性と信仰という立場で対立してきた哲学と宗教。古代ギリシアから現代までの本質的な関わりを検証。
「生と存在の意味を問う」という共通課題を持ちながら、哲学と宗教は理性と信仰や神という立場で対立してきた。古代ギリシアから現代までの西洋思想史を通して本質的な関わりを検証。
内容説明
宗教と哲学における本質的な重なり合いを包括的に検証しながら、これまで一面的な見方からの脱却を試みる。古代ギリシアからラテン、中世世界を中心に論じつつ、桎梏から解放された近現代の姿を浮かび上がらせ、宗教と哲学の関わりの変遷を丹念に解説。
目次
序 宗教と生の意味
第1章 宗教と近代科学
第2章 宗教哲学の広大な領域
第3章 宗教の本質―信念をともなう祭祀
第4章 ギリシア世界
第5章 ラテン世界
第6章 中世世界
第7章 近代世界
結論
著者等紹介
越後圭一[エチゴケイイチ]
1977年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程(宗教学専攻)研究指導認定退学。トゥールーズ第2大学博士課程修了(哲学博士号取得)。神戸市外国語大学にて非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さえきかずひこ
13
宗教と哲学の切っても切れない関係について関心がある方におすすめの一冊。著者はまず現代の科学と宗教の関係について考察し、具体的に宗教と哲学の関係を問うてゆく。プラトンは古代ギリシア神話から多くの示唆を受け、その哲学を打ち立てたこと。この記述は長く、著者が彼の哲学を深く重んじていることが伝わってくる。また、中世のスコラ哲学はキリスト教を護るために発展した。そしてとくに近代においてはヘーゲルとハイデガーに力点を置いて論じたあと、宗教も哲学もその根底で善きものを追究して成り立つ知の体系であることを示し結んでいる。2019/12/20
ラウリスタ~
13
宗教に関わる哲学という広く、長い問題を、客観的に全体的に記述しようとしているためか、前提知識がない人間からするとものすごく難しい。短すぎて、逆に分かり難いというか。やはりこういうタイプの話題ってのは、なにかの立場に依拠して、批判し、支持してくれるのなら分かりやすいのだけれども。「宗教は民衆のアヘン」という良く知られたマルクスの言葉は、実はカントに先取られたものであり、また19世紀には(アルコールやビールと違い)ポジティブなイメージを持っていたものだったとか(ダンディ、裕福)そういう注は面白かった。2015/06/18
うえ
4
今年出た本。中身は濃い。マイモニデスやファーラービーについても言及は多々ある「ルソーやカントといった思想家たちなら道徳の命令は神の命令と見なしうると言うかもしれないが…それら命令の起源は純粋に道徳的だとも言うだろう」「ガダマーが述べたことは間違いではない。彼によればアリストテレスはその師プラトンにおいて私たちの世界からイデアが分離していることをたえず批判したのだが、アリストテレスが第一動因の至高の超越性を措定するとき、おそらく彼こそが分離を考えたほんとうの思想家なのである」2015/03/31
原玉幸子
2
祭祀と信念で構成される宗教が、幸福を求める形而上学で哲学と融合し、カトリック教に服従した「平凡な」時代の中世を経て、近代以降の哲学者や社会学者マルクスに喝破される、親和性のある宗教と哲学の、起源と融合と相反の歴史の解説で、「現代と未来には、宗教はどう語られるのか」を考えることになります。宗教が何たるやに思い詰めることはありませんが、ヘーゲルが、哲学は宗教に優っている、といみじくも断じた「宗教は感性的表象の虜になったままであり……」との表現は、私に、その親和性を再考させます。(◎2020年・夏)2020/07/10
Go Extreme
1
教の本質:信仰 儀式 祭祀 宗教的体験 象徴 宗教的信念 精神的支え 宗教的共同体 宗教と哲学:宗教哲学 存在の意味 生の目的 アウグスティヌス 信仰と理性 哲学的探求 宗教的問い 社会的機能:道徳的規範 社会統合 教育的役割 精神的浄化 政治的正当化 宗教的伝統 宗教と科学:近代科学 啓蒙主義 科学的合理性 名目論 進化論 宗教と科学の対立 思想家:マルクス ニーチェ フロイト プラトン アリストテレス ソクラテス 歴史的展開:ギリシア宗教 中世キリスト教 近代批判 現代宗教 文化的背景 宗教の復活2025/03/28