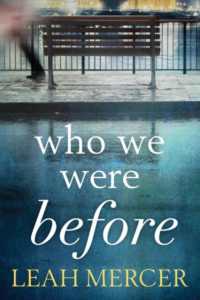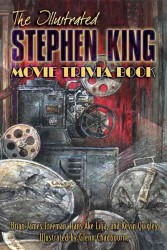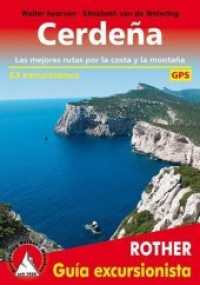出版社内容情報
最新の自然科学の知見から、いま必要な〈知〉の領域を考える。東大駒場の人気公開講座より、学内外の研究者による20講義を収録。
内容説明
未来が見える!講義で感動したことありますか?ノーベル賞受賞者から大ベストセラー執筆者まで、“東大駒場”で数百人を前に語られた科学と技術のこれから。
目次
1 生を見つめなおす(時間とは何だろう―ゾウの時間 ネズミの時間;近代科学と人のいのち ほか)
2 自然の叡智に学ぶ(飛行機はどうして飛べるのか―未来の航空機を考える;柔らかいロボットをつくる―粘菌に学ぶ自律分散制御 ほか)
3 日常に寄り添う(ヒトのこころの測定法;音の科学・音場の科学 ほか)
4 宇宙の根源を問う(超新星ニュートリノで探る大質量星の最後の姿―超新星爆発;素敵な数、素数 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おおた
17
文系の人ほど理系の入門書を読むべきだと思うのです。話題になった鼠と象の時間のちがいから、ニュートリノで何が分かるのかまで、文系のわたしにも分かりやすく書かれています。特に印象に残ったのが、早晩枯渇が見込まれる化石資源について、微生物や菌類を使ったバイオマスによって乗り切ろうとする五十嵐圭日子さんによる研究。原発に反対するのは簡単だけど、代替に何を使えば経済的な損失を少なくして乗り切ることができるのか。政治への批判は文系理系を越えて大局を見据えた解決策を考える時期になったのだと気づかされる一冊。2017/10/29
zoe
15
高校生向け金曜日の講義が発端になり本にしたものと後書きに。配信も実施しているようで、URLを紹介。勿論、一般向けとも。時々横ぐしを通した本を読むと、一とかⅠがLとかEになり冊や田になっていく、そんなイメージ。自分が中高生の時は、学校の先生とか有名な予備校の先生ぐらいしか情報源のイメージはありませんでした。テレビの録画もテープの時代。今は選択肢が多くて羨ましい限り。2020/09/05
たばかるB
6
中学生程度?向けくらいに書かれた本。目を惹く内容も多かったが、よくある社会問題の自論を述べてるだけ(のようなもの)や、wiki併用でないと読み通せない程学術用語並べているような内容もあった点は惜しかった。さらには「最先端」とは言っても所詮は日本の大学。見栄えのある研究分野を取り上げてうまく全体を装飾しているようなボカした印象だった。2018/09/28
Go_with_twill
2
教授陣のエッセイみたいな構成で、気軽に読めました。自分の研究を絡めつつ、いろんな視点に拡張されてて面白かったです。参考文献がついてるのも良かった。2017/10/31
かず
1
知的好奇心が刺激されて、もちろん興味のある分野に限るけど深く知りたいという気持ちにさせてくれます。2024/08/31
-

- 電子書籍
- ざつ旅-That's Journey-…