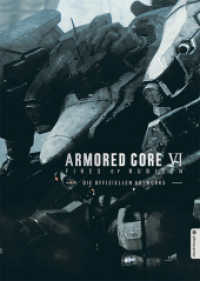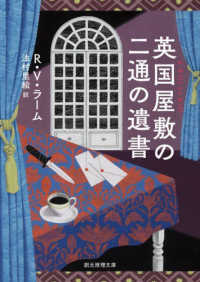内容説明
独ソ戦からその最期まで「人間スターリン」の実像に迫る画期的な伝記。英国文学賞「歴史部門」受賞作品。
目次
第7部 戦争―天才の躓き 1941‐1942
第8部 戦争―天才の勝利 1942‐1945
第9部 危険な帝位継承ゲーム―1945‐1949
第10部 牙を失った虎―1949‐1953
著者等紹介
モンテフィオーリ,サイモン・セバーグ[モンテフィオーリ,サイモンセバーグ][Montefiore,Simon Sebag]
1965年生まれ。英国の歴史家。英国王立文学会会員。その著作は35の言語に翻訳されてベストセラーとなり、広く世界で賞賛されている。Catherine the Great & Potemkinは英国の「サミュエル・ジョンソン賞」、「ダフ・クーパー賞」、「マーシュ伝記文学賞」の最終候補作品となった。『スターリン―赤い皇帝と廷臣たち』は「英国文学賞」(歴史部門)を受賞した。若きスターリンを描いた続編の『スターリン 青春と革命の時代』は「ロサンゼルス・タイムズ歴史文学賞」(米国)、「コスタ伝記文学賞」(英国)、「クライスキー政治文学賞」(オーストリア)、「政治伝記文学グランプリ」(フランス)などを受賞した
染谷徹[ソメヤトオル]
1940年生。東京外国語大学ロシア語科卒。ロシア政治史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyoshi Hirotaka
19
戦国を終わらせ、鎖国が完成するまで約百年。武力統一、紛争の再発防止、侵略阻止という国の基礎が完成。わが国は、数世代、複数リーダーで対応したが、これを約30年で達成したのがスターリン。粛清、強制移住、近隣の衛星国化という荒技が行われたが、米国に比肩する大国に成長。仮に武道のように「独裁道」があるとする。宗家はスターリン。ヒトラー、毛沢東は高弟。その後に、金日成、チャウシェスク、ポルポトと続き、世界に拡散。今やAIやIoTは独裁の強力なツール。次の悲劇は世界規模化する。しかも、権力継承には未だに成功例はない。2019/01/19
てれまこし
14
愛されたいと願いつつも、自分の崇拝者をバカにしてる。ナルシシズムの典型的な症状がスターリンにも見られる。フロイトはナルシシストに人格者になるか犯罪者になるかという素質を見出したが、スターリンの場合にもこれが当て嵌まる。愛されるために権力を求め、対等な同志ではなく善悪判断のできない卑屈な廷臣に取り巻かれる。そして腹を割って話をする相手がなくなり孤独になる。この孤独が猜疑心となって粛清を呼ぶ。そうして自分をさらに孤独に追いこんでいく。彼自身、自分が作り上げた独裁体制に不満を漏らす(「なんでもわしに頼るな!」)2021/05/21
健
13
ようやく読み終わった。スターリンを中心にして生き残りを競う古参ボルシェビキのどたばた喜劇のようだ。その裏で数千万人が粛清されたって言うのだから恐ろしい。スターリン批判をして評価を上げたフルシチョフでさえ、ウクライナて数百万人を粛清していたのだから、ソ連共産党は狂っていたとしか思えない。こんな政権で70年間の東西冷戦の一方の親玉を築き上げたわけで、一体全体どうなっていたのか。。。2019/05/02
柳瀬敬二
10
下巻はバルバロッサからスターリンの死まで。二千万を超える死者を出しながらもWW2を乗り切ったスターリンは、戦後になってもレニングラード派や、医師、ユダヤ人を対象に粛清を辞めなかった。歳とともに被害妄想を強めていくスターリンに対し、廷臣たちはその最期の瞬間まで、憎愛入り混じった複雑な感情を抱き続けていた。現代の我々から見れば狂気の沙汰としか思えない粛清、対決、自己批判、拷問といった数々の行動も、マルクス・レーニン主義とスターリンの絶対性という観点から見れば筋の通った行為だったのだろうか。2015/06/29
nonnomarukari(ノンノ〇(仮))
4
今回はヒトラーの強襲からスターリンの死までを描いている。戦争中でも脱走兵・反乱分子とみられる人物を粛清しまくってどうなのと感じた。今回も収容所送り・銃殺される人がたくさんいたんだけど、その性格が陰謀やら政治目的から単なる年寄りの猜疑心に変わっているように思えて怖くなってきた。娘のスヴェトラーナがベリヤの息子に恋してたなんて知らんかったな。医者を疑って粛清したおかげで危篤状態なのに部下がなかなか医者を呼ぶ事ができなかったのは彼らしい最後といっていいのだろうか・・。2011/04/14