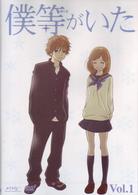目次
人は異なる手段で、同じような目的に到達する
悲しみについて
われわれの情念は、われわれの先へと運ばれていく
本当の目的がないときには、魂はその情念を、いつわりの対象に向かってぶちまけること
包囲された砦の司令官は、そこから出て交渉すべきなのか
交渉のときは危険な時間
われわれの行動は、その意図によって判断される
暇であることについて
うそつきについて
口のはやさと口のおそさについて〔ほか〕
著者等紹介
宮下志朗[ミヤシタシロウ]
1947年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。専門はフランス・ルネサンスの文学と社会、書物の言語態(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
masabi
25
【要旨】モンテーニュが日々の思索を綴ったもの。第一分冊。【感想】精神の暴走の目録と言うだけあって話題も「哲学することとは死に方を学ぶこと」という有名なものからEDに関することから多岐にわたる。話題がころころ変わるのが読みにくさを助長しているようにも思えるが、時折鋭い考察が述べられていてふとしたときに読みたくなるかもしれない。習慣についてと子の教育については今でも有用だ。二巻も読むことにする。2017/02/07
マッピー
16
最初の方はエッセイと言うよりも、哲学や歴史についてを読んでいる気がしました。塩野七生の『ローマ人の物語』、ダンテの『神曲』、佐藤賢一のフランス史物などを読んでいたおかげで、思ったほどつらくはありませんでしたが、やっぱり知識の不足が残念だなあ。ところで、「エセー(随想録)」というので、「枕草子」や「徒然草」のような身辺雑記から発するあれこれかと思ったのですが、それよりちょっと宗教・哲学寄り。宗教戦争についてなどは、書いた当初は時事問題くらいの感覚だったのかしら。今読むとがっつり歴史なのですが。 2023/03/09
ルル
14
モンテーニュからは【社会観察の仕方】のヒントを、そして、訳者からは【日本語表現】の豊かさを学べました。要再読本❗️2019/09/03
吟遊
11
話題がバラバラなのと、古典からの(プルタルコスとセネカがとくに好きらしい)引用がとても多いので、読むのに根気がいる。読み始めて、だんだんと著者のペース、文体に慣れてゆくと楽しくなる。高尚な教育論、徳と哲学について語れば、性的不能、戦場での恐怖についても語るというように、分け隔てがない。大変に謙虚で、自分のなかを探求し、自分のなかに発見を求める、と言いつつも、自分語りをせず、あくまで出来事を例示するところが豊かな知性の一端。原典にした「版」の問題についてはあとがきの方に詳しい。2016/11/14
はなよ
9
現代で例えると、ただの本好きのおっさんが書いているブログ記事みたいなものを、ありがたく読んでいる私は奇妙だなぁと思うんだけど、本当の文学っていうのはこういう「自然と湧き上がってきた言葉」の中から作られるのかもしれない。2017/09/13