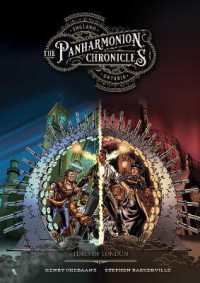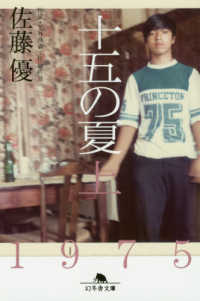出版社内容情報
「あさまんじゅうに昼うどん」は物日におけるきまりもの。小麦、さつまいも、狭山茶、深谷ねぎ、岡部の大根など自慢の作物もいっぱい。街道のうまいもの、鋳物工場の給食まで収録。
内容説明
この本は、大正の終わりから昭和の初めころの埼玉県の食生活を再現したものです。
目次
秩父山地の食―炭を焼き、柿もたわわな山里に育つ麦と桑
大里・児玉の食―お蚕さんの世話上手、めん打ち上手は女の甲斐性
入間台地の食―乾いた台地に茶の樹の緑、いも掘る里に機の音
北足立台地の食―中山道の町で商い、大地の恵みを食して暮らす
東部低地の食―開田の努力実った湿地帯、稲刈る鎌穂の重み
川越商家の食―蔵造りの街の折目正しい暮らしと小江戸の味
鋳物工場の共同給食―小僧さんたちへの「栄養食」が鋳物の町を支える
武州の風土が育てた伝統の味
人の一生と食べもの
埼玉の食とその背景
埼玉の食 資料
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
arry
3
都道府県分発行されているのだろう。他の都道府県も図書館でら読んでみたい。昭和30年頃に調べた郷土食の本。細かく地域別に分類し詳細な内容。昭和の高度成長期以前迄の食の様子がわかる。2024/10/01
YUPO Tetesi
0
その土地でとれるもので食事を組み立てる。そういう習慣が大事なのだと思う。また、人の一生と食べ物という視点。勉強になった。次は生まれ故郷・青森の食事をあらためて学びたい。2024/10/25
ひげめがね
0
このシリーズは面白い。県ごとに伝統的な料理をヒアリングしてまとめてある。畑を見る目が変わります。2008/04/01
しいかあ
0
自分の偏った食生活がほぼ地元の食文化をきちんと継承したものだったと知ってわりと驚いている。内陸部で海産物が手に入りにくいから普段は煮干しくらいしか出汁がなくて味噌と醤油で味付け、動物性たんぱく質がほとんど手に入らないから野菜と穀物中心の食生活っていうの、出汁の概念を理解してなくて放っておくと野菜ばかり食ってた以前の自分の食生活に当てはまりすぎる。そもそも料理に酒やみりんを使うという概念が欠けているんだよな。そういう文化で育ったのでいまだに料理で酒を使う意味があんまり実感できてない。2022/01/21