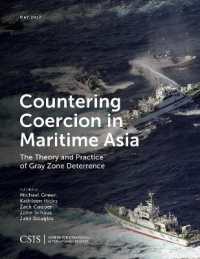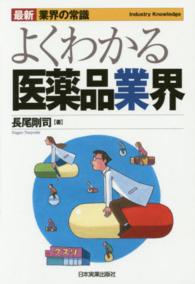内容説明
「いろいろ大変だが、何よりつらいのは孫が戻って来ないこと」と、被災地、南相馬に生きる人たちはいいます。家族のつながり、地域のつながりがとぎれてしまいました。病院のベッド、看護師さん、ヘルパーさんの数も足りません。人々はこれからどうやって、「いのちのバトン」を渡していけばよいのか―。そこで、地域の砦、市立総合病院のドクター「ねもっち」たちは、まちに飛び出すことにしました。地域全体を大きな病院に見立て、それぞれ、お家がベッド、ナースコールは携帯電話やご近所さん、というふうに。ITも活躍します。いろんなアイデアを持ちより、地域の人をまき込んで、いのちを大切につなぐ「まちづくり」を始めています。
著者等紹介
國森康弘[クニモリヤスヒロ]
写真家、ジャーナリスト。1974年生まれ。京都大学経済学研究科修士課程修了、神戸新聞記者を経てイラク戦争を機に独立。イラク、ソマリア、スーダン、ウガンダ、ブルキナファソ、カンボジアなどの紛争地や経済貧困地域を回り、国内では、戦争体験者や野宿労働者、東日本大震災被災者の取材を重ねてきた。「あたたかで幸せな生死を伝えること」「いのちの有限性と継承性」をテーマに、近年では看取り、在宅医療、地域包括ケアの撮影に力を入れ、滋賀・永源寺地域の花戸貴司医師らに同行取材している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
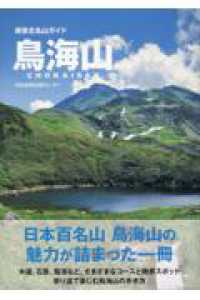
- 和書
- 鳥海山 南東北名山ガイド