内容説明
明治以来の近現代日本の学校教育の主流である「地元を捨てさせる教育」に対して、地下水脈のような「土地に根ざす学び」の系譜があった。「土の教育」「郷土教育」「デンマーク型教育」、江渡狄嶺、三澤勝衛らが求めたものを、「いま・ここを掘り下げる学び」として現代的に光を当てる。歴史と現代の実践を架橋し、自分が暮らす土地の価値を発見し、育てていく地域再生学としての「場の教育」の理念と可能性を示す。
目次
第1部 場の教育の可能性(いま地域と教育を問い直す;多様な地域を相互承認する;土地に根ざした教育の歴史に学ぶ;場の教育が希望を創る)
第2部 場の教育の実践(学びの場としての農山濃村;TAPPO「南魚沼やまとくらしの学校」の誕生;TAPPO「南魚沼やまとくらしの学校」の活動;地域づくりに大切なもの)
著者等紹介
岩崎正弥[イワサキマサヤ]
1961年静岡県生まれ。京都大学大学院農学研究科農林経済学専攻博士課程修了(農学博士)。愛知大学経済学部教授。研究テーマは地域づくり論、戦後農山村社会史、農本思想研究
高野孝子[タカノタカコ]
1963年新潟県生まれ。エジンバラ大学教育学部博士課程修了(Ph.D.)。1995年にロシアからカナダまでの北極海を無動力の極点横断に成功。現在は野外・環境教育活動家として、特定非営利活動法人ECOPLUSの代表理事を務める。早稲田大学WAVOC客員准教授。立教大学特任教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
19
大正から昭和にかけての農村での教育と地域づくりの歴史と、「棚田草刈りアート選手権」で知られる南魚沼の活動の現在進行形の記録(この活動の代表・高野本人の記述)を「場の教育」というキーワードでつなぐ。◇石川三四郎や江渡狄嶺など、ここ最近鶴見俊輔の文章などで名前だけ触れていた人々。昭和初めの社会変容に対する農村の側からの取組みは確かに、今の農山村の抱える課題とリンクする。ここで展開される「場」の理論自体はかなり抽象的で、使っていくには他での「場」の捉え方を自分から補完していく必要あり。綴方運動ともリンクしそう。2014/07/06


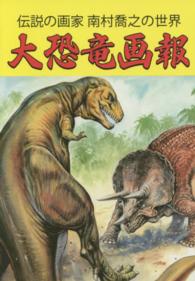
![DVD>陳氏38勢太極拳 [BABジャパン中国武術DVD] 陳家太極拳入門 2 <DVD>](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48942/4894228718.jpg)



