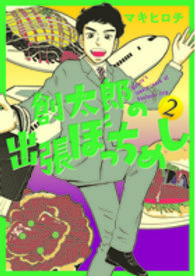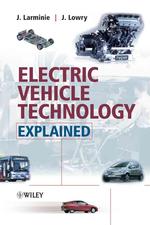内容説明
「自然と人間の営みや関わり」を探究する郷土教育で「地域力」と「自分力」を発見!人を育て、地域を育てる教育の筋道と手法を説く。
目次
序 教育と文化の基本、地理教育をすべての人に
緒論 今こそ地域性=風土性にもとづく文化と産業の建設を―地域振興とその急務
地域からの教育創造(教育にとっての地域教育―地理教育論;地域探求で「地域力」と「自分力」を発見―郷土地理教育論;日本の風土探求の教育―日本地理教育論;世界と地域をつなぐ教育―外国地理教育論(付)「地理通論」教育について)
著者等紹介
三澤勝衛[ミサワカツエ]
1885(明治18)年長野県更級郡更府村(現・長野市信更町)の農家に生まれる。尋常高等小学校卒業後農業に従事しながら勉強し、小学校の代用教員になる。その後検定試験に合格し、地理科教員免許を取得。1920(大正9)年長野県立諏訪中学校(現・長野県諏訪清陵高校)の教諭になり、「自分の目で見て自分の頭で考える」教育の実践と、独自の「風土」の思想を確立し、風土に根ざした地域産業・暮らし・地域づくりに生涯をささげた。太陽黒点の観測・研究者としても国際的に高く評価されている。1937(昭和12)年8月18日永眠(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
0
独学で教壇に立ったという著者による、郷土にこだわった教育実践の集大成の一冊。解説によると、学ばせて、構成・創造させる教育方針に共感を覚えた(p.21~)。風土とは地域の実体で、文化と産業の両立は今日的課題でもあり、重要なテーマを扱っていることがわかった。ラスキンの『建築の七灯』も読まれていることから、その郷土をなんとかするための並々ならぬ気概が感じられる。ものを深く観る、一木一石も考えながら観る、という、観察重視の学習。水車小屋の写真をみれば、小水力発電の脱原発の現代でも非常に有意義なテキストと思える。2012/06/24
-

- 洋書
- Whirlpools