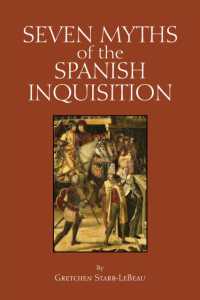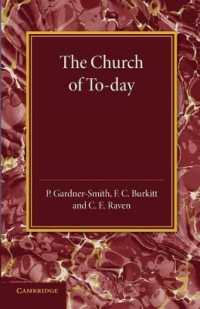内容説明
アスパラガスは、熱帯から亜熱帯まで、世界中で広く栽培されているが、栽培面積あたりの収量は日本がダントツの一位である。とはいえ、アスパラガスは野菜では珍しいユリ科の永年性作物で、生理生態的特性が他の野菜品目と違うため、異なった栽培法がとられ、初心者が栽培を始めるには難しい部分が多いのも実状。本書では、そうした点を踏まえ、ベテランの方はもとより、新しく取り組んでいる方、これからやってみようという方にもわかりやすく、品種、作型、個々の栽培技術について詳しく解説し、新鮮でおいしく、安全で安心して食べられるアスパラガスをつくるにはどうしたらよいかをまとめた。
目次
1 アスパラガス栽培の特徴とねらい
2 作型・品種を見直す
3 植え付け前の準備
4 育苗と定植、一年株養成の実際
5 萌芽から立茎までの生育と管理
6 株養成へバトンタッチ―立茎の判断と方法
7 夏秋どりから収穫切り上げまで
8 作型別管理と作業のポイント
9 魅力を発揮する売り方・経営
著者等紹介
元木悟[モトキサトル]
1967年長野県生まれ。1990年筑波大学卒業。長野県下伊那農業改良普及センター、同中信農業試験場を経て、現在、長野県野菜花き試験場に勤務。これまでに、ピーマン「ベルマサリ」、トマト「桃あかり、なつのしゅん」、エンドウ「さや姫」、ダイズ「さやなみ、ほうえん、玉大黒、すずこまち」など共同育成。1998年からアスパラガスの研究に従事
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
里のフクロウ
0
1ヘクタールの畑にアスパラガスの定植をしたときに参考とした本書を10年ぶりにひもといた。理由は「土づくり」についての記述内容を確認するためである。土壌医として土づくりの専門化を目指している今、アスパラ圃場の土づくりに失敗した経験を反省する意味を込めてである。こうした観点から見えてくるのは、技術書なのか理論書なのかという本書の持つ性格についてである。その何れでもなく中途半端なものだ。少なくとも農業技術を記してはいないことを理解した。それを理解せずにマニュアルとして利用したことに誤りがあったことを反省した。2017/03/10