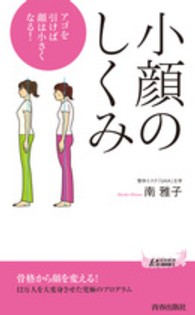出版社内容情報
依存症、自傷・自殺等、多様な当事者の心理をどう理解し関わるか。大好評を博した『こころの科学』特別企画に新稿を加え書籍化。
内容説明
「困っていません」と言われた時、あなたならどうしますか?虐待・貧困、いじめ、自傷・自殺、依存症、性被害…さまざまなフィールドから援助と援助希求を考える。『こころの科学』大好評特別企画、5つの章を加え待望の書籍化。
目次
1 助けを求められない心理
2 子どもとかかわる現場から
3 医療の現場から
4 福祉・心理臨床の現場から
5 民間支援団体の活動から
座談会 「依存」のススメ―援助希求を超えて
著者等紹介
松本俊彦[マツモトトシヒコ]
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長。1993年佐賀医科大学卒業。横浜市立大学医学部附属病院にて臨床研修修了後、国立横浜病院精神科、神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科を経て、2004年に国立精神・神経センター(現、国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所司法精神医学研究部専門医療・社会復帰研究室長に就任。以後、同研究所自殺予防総合対策センター自殺実態分析室長、同副センター長を歴任し、2015年より現職。2017年より国立精神・神経医療研究センター病院薬物依存症センターセンター長を併任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆいまある
93
こころの科学での連載が元になっている。個性派ぞろいの著者による「助けてが言えない人々」。いじめ当事者、薬物依存、ギャンブル依存、ホームレス、認知症、未治療の統合失調症、意外なところでは男性の性被害者、ゲイ+HIV感染者。「助けて」と言わせることが目的ではない。医療にできることもたかが知れてる。知識と想像力を持ち、孤立させない工夫を続けること。そして医療従事者もまた、助けてが言えない人であることが多い(私もそうだ)。ひとつの物に依存しているのが依存症。依存先が沢山あるのが自立。うん。確かに。KU2025/01/29
たかこ
58
支援を求めるのにも力が必要。言えばいいのに、助けてが言えない人がたくさんいる。援助希求力をつけることが大切だと言われるけれど、そう簡単な話ではない。当事者の複雑な生い立ちや環境からSOSすら出せないということが起きている。子ども、医療、福祉の現場からの報告を読んで、本当に簡単なことではないと知る。「自立とは、依存先を増やすこと」、依存症は「依存できない病」だとも言える。誰にも頼れないから、モノに依存するしかないのだ。『ケーキの切れない非行少年たち 』にも「取手は内側にしか付いていない」とあった。同じだ。2023/09/29
ネギっ子gen
55
【副題にもなった「SOSを出さない人に支援者は何ができるか」が書かれた本】《共感①》<自傷行為は「誰かにアピールしたり、構ってほしくてやっている」のであり、その意味では「助けて」というメッセージを頻繁に発しているのではないかと思われる人もいるかもしれない。/しかし、実は他者に気づかれるような自傷行為は、全体の中でもごくわずかなものでしかないことはあまり知られていない。/ほとんどの自傷行為は誰にも見つからない一人きりの空間で行われており、自身の不快感情と孤独に向き合う対処行動だといえよう。言い換えるなら、⇒2020/03/08
ゆう。
38
SOSを表明することができない人たちに、支援はどのようにしていけばいいのか。道徳的に詰め寄るのではなく、依存することが大丈夫な支援を考える必要がある。SOSを出せないことを自己責任化してはならない。社会によって声をあげられなくさせられた人たちに求められる支援とは何か考えさせられた。2019/10/04
コージー
32
★★★★☆『こころの科学』特別企画を書籍化。「助けて」が言えない人に支援者はなにができるかを、各分野の第一人者19名が解説。SOSが出せない人よりも、とりまく社会や環境に目を向けて問題点をあぶりだす。かなり難しい内容だが支援者にはぜひ読んでほしい良書。【印象的な言葉】生きるには、生きる意味を追求するのでなく、「死ねなかったから生きる」という軽いノリでいい。「生きるか死ぬか」という座標軸をずらすのである。2019/08/17
-

- 電子書籍
- あなたのハニーは転生から帰ってきた【タ…
-

- 電子書籍
- 東京みちくさ案内