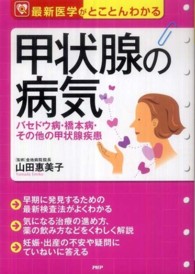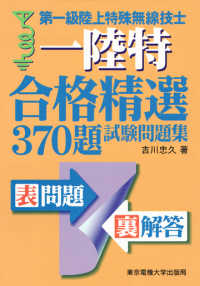出版社内容情報
人工知能と人間が共存する社会において、知性をどう認識し、人間はどのように生きればよいのか。3名の著者がこの問題を論じる。
内容説明
私たちはどう生きるか。人工知能の進展により、ゆらぎはじめた人間の知性。新しい時代の教養。
目次
第1部 人工知能―ディープラーニングの新展開(人工知能のこれまで;ディープラーニングとは何か;ディープラーニングによる今後の技術進化;消費インテリジェンス;人間を超える人工知能)
第2部 人工知能と世界の見方―強い同型論(人工知能が「世界の見方」を変える;認知構造はどう変わろうとしているのか;強い同型論;強い同型論で知能を説明する;我々の「世界の見方」はどこからきてどこに向かうのか)
第3部 人工知能と社会―可謬性の哲学(人工知能と人間社会;自由主義の政治哲学が直面する課題;人工知能とイノベーションの正義論;世代間資産としての正義システム;自由の根拠としての可謬性)
著者等紹介
西山圭太[ニシヤマケイタ]
1963年、東京都生まれ。1985年、東京大学法学部卒業後、通商産業省入省。1992年、オックスフォード大学哲学・政治学・経済学コース修了。中央大学大学院公共政策研究科客員教授、株式会社産業革新機構執行役員、経済産業省大臣官房審議官、東京電力ホールディングス株式会社取締役などを経て、経済産業研究所コンサルティングフェロー、経済産業省商務情報政策局長
松尾豊[マツオユタカ]
1975年、香川県生まれ。1997年、東京大学工学部電子情報工学科卒業。2002年、東京大学大学院工学系研究科電子情報工学博士課程修了。博士(工学)。スタンフォード大学CSLI客員研究員、シンガポール国立大学(NUS)客員准教授などを経て、東京大学大学院工学系研究科教授
小林慶一郎[コバヤシケイイチロウ]
1966年、兵庫県生まれ。1991年、東京大学大学院計数工学科修士課程修了(工学修士)後、通商産業省入省。1998年8月シカゴ大学よりPh.D.(経済学)取得。経済産業研究所上席研究員、慶應義塾大学経済学部教授などを経て、公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹。慶應義塾大学経済学部客員教授、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹などを兼務。著書:『日本経済の罠』(共著、日経・経済図書文化賞受賞、2001年)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
kaze
海星梨
Kyo-to-read
ぼの
-
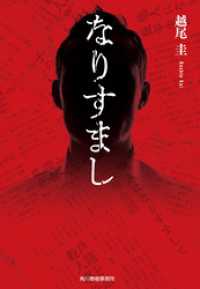
- 電子書籍
- なりすまし ハルキ文庫
-
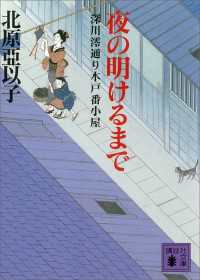
- 電子書籍
- 夜の明けるまで 深川澪通り木戸番小屋 …