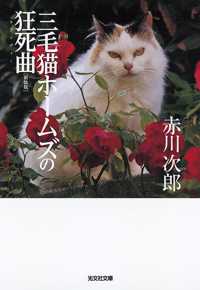内容説明
メンタルヘルスの専門家がイチから解説!心と体の結びつきから考える注目理論の“役立つ”入門書。
目次
序章 悩みをこじらす人の共通点
第1章 「ポリヴェーガル理論」とはどういう理論?
第2章 3色についての理解を深めよう
第3章 ポリ語で生活してみよう
第4章 緑を増やす方法
第5章 悩み方や体験を変えよう
第6章 体にもっと関心を
著者等紹介
吉里恒昭[ヨシザトツネアキ]
臨床心理士、公認心理師、医学博士。フォーチュンビレッジ代表。株式会社DMW取締役。心療内科、精神科の現場でカウンセラーとして20年以上の臨床経験を持つ。うつ病、依存症、PTSD(トラウマ)など、様々なメンタル疾患に対して「からだ・こころ・発達・対人関係」の側面からセラピーを行っている。専門的アプローチはブリーフセラピー、ナラティブアプローチ、マインドフルネス、ポリヴェーガル理論、整体など。2020年から支援者(カウンセラーなど)を対象としたオンラインスクール(DMWクラブ)を開講。最新メンタルヘルスやポリヴェーガル理論を支援者が使えるようになるための学び場を提供している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
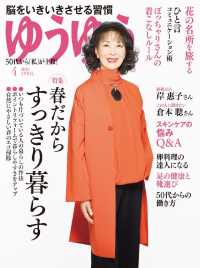
- 電子書籍
- ゆうゆう - 2019年4月号
-
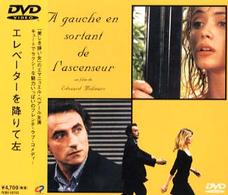
- DVD
- エレベーターを降りて左