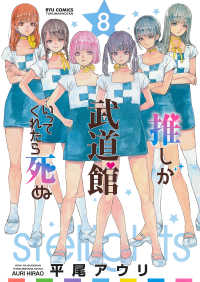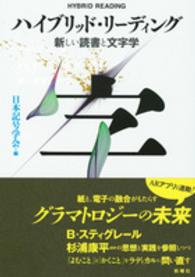出版社内容情報
人工知能が人類を超えるシンギュラリティ(特異点)にどう立ち向かうかにロボット工学者が答える。
内容説明
人類最後の発明が人類を滅ぼすのか?それとも―。気鋭のロボット工学者が問う、人工超知能とシンギュラリティの未来!
目次
序章 シンギュラリティを前に
第1章 シンギュラリティがなぜ問題になるのか?
第2章 私たちはどこから来たのか?
第3章 科学技術の進歩と人類の進化
第4章 そして、人類のゴールへ
終章 シンギュラリティ後の人類ビジョン
著者等紹介
台場時生[ダイバトキオ]
某大学理工学部准教授。研究分野はロボット工学、特にヒューマノイドロボットの運動制御に関する研究に従事。ロボット、人工知能と人間の共存の在り方、さらに人類そのものの未来について考察を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えも
17
普段はできるだけマイナスの感想を書かないようにしていますが、でも、この本、浅いです w 著者はロボット工学者で、シンギュラリティ(技術的特異点)=科学技術の進歩するスピードが予測不可能なほど高速になる時を指す言葉。そんな時代の到来を示すキレキレの研究成果を期待したのですが、そうじゃなくて、その先の人類の未来を考察した内容でした。しかも、テレビなんかで聞いた程度の知識をもとに、素人考えで浅い論考をしているだけ。…なんて言い過ぎですが、一応最後まで読んでみて、残念感が満載です。2016/10/22
tetsu
12
★3 シンギュラリティのその先を見据えた哲学書。 宇宙誕生、生物進化、人間の幸福、人類のゴール、壮大な話。2018/08/14
inami
9
◉読書 ★3 「超人工知能が・・」という題名だが、シンギュラリティのその先にある未来をテーマにしているので、AI関連の内容はとても薄いです。そんな中、気になったところ2点、①「クオリア(質感)と意識」について、自分の”青色”と他人の”青色”(自分にとっては赤色)が違っていても、確かめることができない、②ピアノの演奏が聞こえるのは音色が伝搬しているのではなく、正しくは(当たり前だが改めてそうか・・と)「無音のまま空気が揺れているだけ(頭の中で鳴っている)」、んん〜・・AIの話どこへ行っちゃったの・・って感じ2017/12/25
GASHOW
4
特化型人工知能ANIは世界に普及している。よく目にするAIはこのことだ。ドラえもんのような存在を汎用人工知能AGIで、カールツワイス予測は2029年だ。人間のようなことができる人工知能は現時点では幼児レベルだというし、そもそも意識をつくりだせているかどうかは不明だ。人工超知能はそれをこえたASIで特異点を超えた人類よりも賢い存在だという。コンピューターが発明されて100年で現在のような社会が訪れているから、シンギュラリティは個人的にはあるかもしれないと思う。知能をもった側は冷酷なことをするとも思う。2020/02/14
りょうみや
4
人口知能が人間を超え自己発展できるほどの知能を持った時の未来を考えるのが主題なのだが、人類史、脳、幸福論などサブのトピックの総量が多く、本全体で見た時に軸が分からなくてまとまっていない印象。個人的には人工知能が発展する未来は楽しみで楽観的。2016/05/03