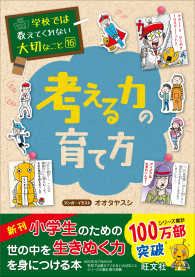- ホーム
- > 和書
- > ビジネス
- > 仕事の技術
- > リーダーシップ・コーチング
出版社内容情報
組織のリーダーに向けて、科学的な「行動分析学」を用いて職場をマネジメントする手法を紹介!
内容説明
行動分析学とは「人がなぜそのように行動するのか」について法則を見つけて探究しようとする心理学の一分野です。本書ではこの手法を用いて組織で働くリーダーが人を動かす際のポイントを解説します。
目次
第1章 企業は行動なり(行動なくして業績なし;リーダーの行動が原動力 ほか)
第2章 業績をつくる行動公式(行動は随伴性で変わる;随伴性なくして、行動なし ほか)
第3章 リーダーシップを原動力に(業績にインパクトを;期待をわかりやすく伝える ほか)
第4章 リーダーシップを育てる仕組み(リーダーを育てる;ダブルPBL ほか)
第5章 よくある疑問や誤解(部下を叱ってはいけないのですか?;褒めすぎたら部下がつけあがりませんか? ほか)
著者等紹介
島宗理[シマムネサトル]
1964年埼玉県生まれ。1986年、千葉大学文学部行動科学科卒業。1989年、慶應義塾大学社会学研究科修士課程修了。1992年、Western Michigan University心理学部博士課程修了、Ph.D.取得。鳴門教育大学を経て、法政大学文学部心理学科教授。専門は行動分析学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Yuma Usui
28
部下を率いるための行動分析学の手法の紹介。リーダーの行動と部下の行動の掛け合わせが業績を決めるという式はしっくりきた。いくつかある増やして欲しい部下の行動のどれに焦点を当てるかを考え、それを標的行動として継続的に好子による強化を行うという考え方や、シェーピングにより徐々に好ましい標的行動に変化させていくという段階を踏む方法も興味深い。2021/01/11
たこ焼き
3
今までやったことがないことをやることは体や感情が強い違和感を感じるものである。しかし変わりたいならその違和感を乗り越える。行動を依頼したらフォローする。フィードバックこそ改善の源泉なので、フィードバックに敏感になること。一方でフィードバックの真意を誤解しないように意識する。部下の行動は上司の考えの鏡である。(上司がやっているのだからいいいや、というように。)課題を文化や性格のせいにしていると何も変わらない。行動がしっかりされているかのフォローはできるだけ数値化。(ただやりすぎると行動そのものが目的になる)2020/08/17
牛タン
3
行動に介入することで業績に繋げる手法。性格や感情に働きかけるのではない点が特徴。行動指標を具体的に設定し、できれば褒める(好子)ことで、目標にした行動を強化できるという。即時性と言語化が重要らしい。とても良さそうなので使ってみたいと思った2018/03/10
☆ツイテル☆
2
フライヤー2022/01/26
K
2
ポジティブな行動マネジメントについて書かれた一冊 ある行動を起こさせるには、その行動をした要因、行動後の結果を分析する。行動後の結果が行動した者にとって良いと感じると、また行動したくなることになるため、そのサイクルを回して行くのが良い。2018/04/17
-

- 電子書籍
- 【分冊版】治癒魔法の間違った使い方 ~…
-
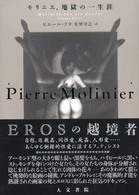
- 和書
- モリニエ、地獄の一生涯