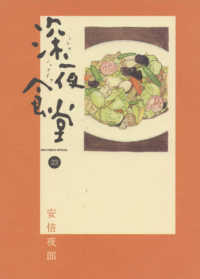内容説明
論理はすべての「知」の基礎である!「読む、書く、聞く、話す」以前の「考える」ためのルール。
目次
序章 「論理を学ぶこと」の困難
第1章 論理と論理ならざるもの
第2章 「論理」から「論理学」へ
第3章 論理学の規則を学ぼう
第4章 論理学の原理を確かめよう
第5章 「論理的な誤り」を避けるために
終章 演習問題
著者等紹介
三浦俊彦[ミウラトシヒコ]
1959年生まれ。89年、東京大学大学院比較文学比較文化専門課程修了。現在、和洋女子大学教授。研究分野は、美学、分析哲学、形而上学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
13
論理学について、具体的な論理の例をたくさん挙げながらコミカルかつ明快に解説する本。自分がいかに論理的思考が苦手かがよくわかった。感覚で文章を読み書きするのをやめたい。2019/10/15
袖崎いたる
10
なんというか、ネイティブが母国語の語学書を読むみたいな感じで、具体例を示されれば「ああ、ああいう語用のことね」とわかるけど、その抽象である概念や説明には「おっ…おう…」みたいに及び腰とさせられてしまう感が、ぼくにはある。殆ど暗記物に思えてしまう…てな感じでぼくの論理学嫌いに拍車が掛かった観もある。とはいえ<目的-手段>も<論理-事実>も弁証法的であり、論理と倫理とは手を携えるべきであり、論理学の倫理的側面として寛容の原則――疑わしきは罰すべからずの構えがあることには、論理学にも柔らかさがあることを知った。2015/09/24
yooou
6
そんなには見えてこなかった。著者の性格の悪さみたいなのが見えるのも気になる2017/04/23
G.D
1
この本を読むくらいなら野矢さんだっけ?の論理学を読んだほうがいい。 筆者は論理に対して相当の信頼を置いているようだが、例の選び方や記述から論理が人格を高めるとは言い難いことは筆者自身がよく物語っている。(当然だろうが)はっきり言って、半分読んだあたりから筆者への信頼が無くなり最後は倫理に関する話もあり殆どしっかり読む事はなかった。まあ興味があるなら借りるなどすれば良いのではないでしょうか。買う価値は無いです。2017/09/13
貴登
1
論理学自体は本当にわかりにくいもので、意味が分からないという人が多いのもしょうがないという印象。しかし、5章の語釈や詭弁の解説などは自分の発言を振り返るのに大事な項目であることは事実だと思うので学んで損はないと思う。 この本自体はものすごくわかりやすく嚙み砕いて表面だけ見せているので、通読することができる時点で価値はある。なぜなら、ほとんどの本が途中で断念するからである。著者の発言なのがちょっと気になるが、入門書としては悪くないと思う。2017/05/01