出版社内容情報
○宗教こそ、プーチン・ロシアを読み解く鍵だ。ロシア分析の第一人者が、歴史と文明の観点からロシアと世界秩序の行方を展望する。■現代の国際関係の基礎となっているウェストファリア体制では、宗教的要素を棚上げにして、世界秩序を「主権国家」が織りなすパワー・ゲームとして構想した。イデオロギーの対立を軸にした冷戦もまた、ウェストファリア体制の継続であった。しかし、冷戦の終焉を契機に、イデオロギーに変わる新たな政治の基軸として宗教の役割が見直されることになった。とくにウクライナ自体の東西分裂という構造的問題が次第に明らかになるとともに、世界政治の焦点は、中東危機、IS(イスラム国)問題や難民問題の背景にある宗教に移ってきたといえる。
■このウクライナ危機の最大の要因は、実は宗教である。千年にわたる歴史的・宗教的経緯を抜きに、つまり文明論的・宗教的アプローチ抜きに、今のロシアのアイデンティティ、あるいはロシアとウクライナとの特殊な関係は理解できない。そして、それを理解するカギとなるのが「モスクワは第三のローマ」という世界観だ。
■「第三のローマ」という考え方は、もともと、17世紀半ば、正教とカトリックとの和解という当時の国際的な潮流に乗ってカトリック的要素を取り入れ儀式改革を進めようとした「ニーコン改革」に反発し、モスクワを聖なる都=「第三のローマ」と信じた「古儀式派」といわれる伝統重視の保守派が唱えたものである。
■「古儀式派」とこの改革をめぐる分裂は、これまでのロシア論では無視されてきたが、21世紀に入って、そしてウクライナ危機により注目されるようになった。なぜなら、この宗教改革をめぐる対立問題が、単に宗教上の争いにとどまらず、ロシアとウクライナ、つまりモスクワとキエフとの関係の問題、そしてウクライナ危機やロシアのアイデンティティというきわめて現代的な問題の源流となるものでもあり、さらに、2017年に100年目を迎えるロシア革命の解明にも、ソ連崩壊の理解にもつながる重要な要素だからである。
■プーチンは、ロシアを「正教大国」と表現し、欧米国家ですら放棄しかかっているキリスト教的な価値をロシアが体現するとして、正教とロシアのミッションについて明確に語るようになった。ロシア正教会とローマ・カトリックとの歴史的和解はその成功例の一つだ。この「第一のローマ」と「第三のローマ」との和解は、IS(イスラム国)やシリアをめぐって緊張する中東やウクライナでの現実的紛争を解決する梃子ともなっている。「第三のローマ」としてのソフト・パワーを行使することにもつながるものだ。
■プーチンのロシアはどこへ行くのか――。「ロシアは常に理論の予測を裏切る」というテーゼを提起してきた著者が、文明論的・宗教的アプローチで、政治と宗教とが「交響」する、ウクライナ危機、現代ロシア政治の深層を解き明かす。
序 章 宗教と地政学からロシアを読み解く
第1章 「モスクワは第三のローマ」??ロシアの歴史と現代
第2章 現代ロシアの政治と宗教
第3章 プーチンと保守的ロシア
第4章 ロシアとウクライナ
第5章 プーチンがめざす世界秩序の形成
第6章 東を向くロシア
終 章 揺れ動く世界を読み解く基盤としての宗教
下斗米 伸夫[シモトマイノブオ]
法政大学法学部国際学科教授
ロシア政治分析の第一人者。1948年生まれ。東京大学法学部卒業、同大学法学博士。成蹊大学教授をへて1989年より現職。専門:ロシア政治。主な著書:『ゴルバチョフの時代』(岩波新書、1988年)『ロシア現代政治』(東京大学出版会, 1997年)『ロシア世界』(筑摩書房, 1999年)『日本冷戦史――帝国の崩壊から55年体制へ』(岩波書店, 2011年)『プーチンはアジアをめざす 激変する国際政治』(NHK出版新書、 2014年) など多数。
内容説明
いま起こっているのは「新冷戦」ではない。世界政治の最大の焦点は宗教だ!ウクライナ危機の深層、現代ロシアと宗教との関係、国際秩序の変容を文明論、歴史的視点から解き明かす。
目次
序章 宗教と地政学からロシアを読み解く
第1章 「モスクワは第三のローマ」―ロシアの歴史と現代
第2章 現代ロシアの政治と宗教
第3章 プーチンと保守的ロシア
第4章 ロシアとウクライナ
第5章 プーチンがめざす世界秩序の形成
第6章 東を向くロシア
終章 揺れ動く世界を読み解く基盤としての宗教
著者等紹介
下斗米伸夫[シモトマイノブオ]
法政大学法学部国際学科教授。1948年生まれ。東京大学法学部卒業、同大学法学博士。成蹊大学教授をへて1989年より現職。専門:ロシア政治(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kazuo
だろうぇい
Happy Like a Honeybee
kenitirokikuti
とろ子
-
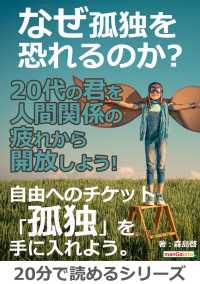
- 電子書籍
- なぜ孤独を恐れるのか?20代の君を人間…
-

- 電子書籍
- ユダヤ知的創造のルーツ





