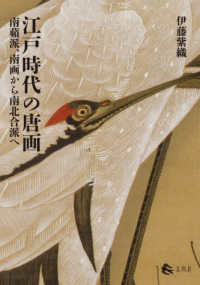出版社内容情報
企業変革の決め手はソフトの部分(体質・風土・マインド・社会的知性・EQ)にある。最新の認知科学・複雑系の科学の知見を採り入れ、「生命体としての企業組織論」を展開。知的エキサイティングに富んだ内容。
目 次
日本企業は創造的経営をいかに取り戻すか ------ 監訳者まえがき
日本語版への序文
プロローグ ------ ビジネス界を生き抜くための知恵
[第一章] マインド志向組織 ------ ネット時代の生命体経営モデル
企業を生命体として捉える
誤りから学び、情報共有するには
大地震が生んだサンタモニカ高速道物語
マインド志向のプロセスが大切
選択したプロセスを常に見直す
結果重視か、プロセス優先か
「過ちを犯すのが人間」であることを前提に考える
脈絡で変わる情報解釈、リフレーミングの重要性
新しい組織像、新しいリーダー像
頭脳の時代には認知能力で差がつく
マインド志向と創造性の共通点
創造的人間の特性
創造的組織の特性
[第二章] 生命体組織への変革 ------ イノベーションを生む巨大エネルギー
複雑系の科学による未来型組織モデル
革命の後に必ず深化の時代が来る
目的を達成し、意味を見出そうとする意志 ---- 自己組織化
カオスから秩序はどのように生じるか
カオスの縁で革命的ブレークスルーが起きる
コンピュータと人間が「共進化」する革命時代
[第三章] カオスの縁で経営する ------ 計画性と臨機応変のバランス
計画を立てすぎる組織は滅びる
半分の計画、半分の臨機応変
鉄道モデルからタクシーモデルへ
人こそ真の財産
自己組織化が創造性に火をつける
[第四章] イノベーションを生む組織構造 ------ 「誤り」を戦略として活用する
階層型組織とネットワーク型組織
創造的緊張を最大限に活用する
パックマンの話
認知能力を高める
視点を変えてみる
老婆か娘か、はたまた・・・
善か悪か ---- 認識と脈絡の問題
組織の創造性を高める戦略
「誤り」を明確にする
「誤り」はイノベーションの源泉
「誤り」を組織戦略として活用する
[第五章] 不確実性を受け入れる ------ カオスから秩序へ、そして再びカオスへ
秩序から偶発型カオスへ
意図的カオスから秩序へ
同時並行的認識のモデル
飽くなき改善に取り組む
怠慢から生じる「秩序からカオスへの移行」
供給者、中間業者、顧客の異なる視点から捉える
継続的再生 ---- IWRAM学習モデル
[第六章] 想像力を広げる ------ 現実世界を解釈する認識フレーム
数、言語、環境 ---- 現実世界を理解するための三つのフィルター
金、時間、人材 ---- 限りある資源の使い方
奪い合えば足らぬ ---- 共有地の悲劇
フィードバック機構による調整 ---- 循環プロセス
権限を伴った責任 ---- 人体のように機能する組織づくり
マインド志向の家族像、組織像
[第七章] 未来を現在に呼び込む ------ 逆向きの思考
変化を受け入れる計画づくり
逆向きに計画を立てる
より少ない資源でより大きな成果を上げる
未来の問題を早くあぶり出す
値決めから逆算してコストを決める
未来を今体験する
[第八章] 新しいリーダーシップ ------ カオスの縁であらゆる困難に立ち向かう
マインド志向組織のリーダーシップ
強烈な目的意識を生み出す
組織の中の「目的」の意味
行動モデル「何事も最適バランスで」 ---- ちょうどいいあんばいが一番いい
組織への適用 ---- 人体に似た概念モデル
全体ビジョンの追求と個別部署の目標達成
現状を定義するためのSMART
目標状態を定義するためのSMART
[第九章] マインド志向組織の実例と教訓 ------ 覚悟を決めて取り組む
数カ月の適応プロセスで変貌
マインド志向組織になるための十三訓
最後に
<付 録> 経営科学の歩み、頭脳時代の幕開け ------ ピラミッドからコンピュータまで
建築家イムホテプのピラミッド
分業の始まり
指揮統制型管理
ヘンリー・フォード ---- 流れ作業
事業部制、専門化、細分化
科学的管理法
コンピュータとコミュニケーション
コンピューターによる解決は万能ではない
謝辞
内容説明
「過ちを犯すのが人間」だが、変化するのは生命の本能だ!誤りを隠さず、情報共有して猛スピードで変革を起こす。複雑系の「進化と革命の原理」から、環境激変に最も敏速に適応する「カオスの縁」の経営を初めて説き明かす。
目次
第1章 マインド志向組織―ネット時代の生命体経営モデル
第2章 生命体組織への変革の道―イノベーションを生む巨大エネルギー
第3章 カオスの縁で経営する―計画性と臨機応変のバランス
第4章 イノベーションを生む組織構造―「誤り」を戦略として活用する
第5章 不確実性を受け入れる―カオスから秩序へ、そして再びカオスへ
第6章 想像力を広げる―現実世界を解釈する認識フレーム
第7章 未来を現在に呼び込む―逆向きの思考
第8章 新しいリーダーシップ―カオスの縁であらゆる困難に立ち向かう
第9章 マインド志向組織の実例と教訓―覚悟を決めて取り組む
著者等紹介
ファーステンバーグ,イーリス R.[Firstenberg,Iris R.]
UCLA心理学部客員教授。UCLA・アンダーソン経営大学院ABCコーポレート・ネットワークのアソシエイト・ディレクター。UCLA心理学部、UCLA工学・応用科学部、アンダーソン校エグゼクティブ教育プログラムで問題解決、意思決定のコースを担当。UCLA優秀指導者賞受賞。ルビンシュタイン教授との共著も2冊ある
ルビンシュタイン,モシェ F.[Rubinstein,Moshe F.]
UCLA工学・応用科学部教授。専門は意思決定論および組織創造論。UCLA・アンダーソン経営大学院ABCコーポレート・ネットワークのディレクター。意思決定やイノベーションのツールを組織内に浸透させる力量について、各方面から高い評価を得ている。IBM、バンク・オブ・アメリカ、AT&T、インテル、ジョンソン・アンド・ジョンソン、GE、TRW、ロッキードなど、大手企業に対するコンサルティング経験をもち、また世界各地に招かれて講演を行っている。教育に関して、UCLA学術評議会賞、UCLA校友会賞、アンダーソン校エグゼクティブ教育賞など数々の賞を受賞している。これまでに発表した著作は9作、論文は100本を超える。主な著書に『問題解決のパートナー』『思考と問題解決のためのツール』『問題解決における概念』など。著作は世界数カ国に翻訳されている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。