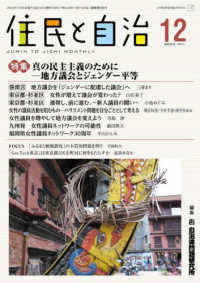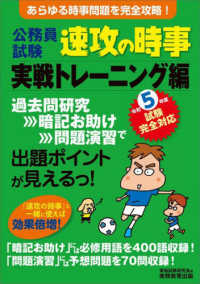出版社内容情報
「近代経済学の祖」といわれる18世紀の大経済学者アダム・スミスの名著を、経済ビジネス書翻訳の第一人者が新訳。労働の価値、貨幣経済の仕組み、分業や貿易のメリットといった経済の本質をわかりやすく伝える。
内容説明
グローバリゼーションに潜む問題を見抜いていた洞察力、国の役割の本質に迫る慧眼。現代社会が抱える課題とその答えがここにある。現代を読み解く「知の遺産」。
目次
第4編 経済政策の考え方(商業中心の考え方、重商主義の原理;国内で生産できる商品の輸入規制;貿易収支が自国に不利とされる国からの輸入に対するほぼ全面的な規制;戻し税;輸出奨励金;通商条約;植民地;重商主義の帰結;重農主義―土地生産物が国の収入と富の唯一の源泉または主要な源泉だとする経済政策の考え方)
第5編 主権者または国の収入(主権者または国の経費;社会の一般財政収入の源泉;政府債務)
解説 『国富論』と現代経済学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
閑居
19
国富論の根底にあるのは労働、特に生産的労働である。アダム・スミスは、労働こそが商品価値の本質であり、生産物こそが労働報酬の本質であると語る。 その考えは法定通貨に慣れ親しんだ私の感覚とはいささかズレていたが、考えてみれば彼の主張は非常に自然で当たり前のようにも思えた。なぜなら、「働いた分だけ報酬が得られる」というのは、本質的で理想的な状況のように思えるからだ。 デイトレーダー、非正規雇用などさまざまな働き方が許容される現代こそ、アダム・スミスに回帰して、今一度労働の本質を考えたい。2009/07/27
たかしくん。
18
遂に歴史的な名著を読了しました。題名だけお借りして恐縮ですが、まさに「経済は世界史から学べ」を地で行った、丁寧な史実の検証と現状の分析。今でも充分通用する経済学のバイブルと呼ばれる所以でしょう。そして、上巻でも申した通り、経済学ばかりでなく歴史学や当時の思想まで踏み込んだ、社会科学の総合的な論文と言えます。更に感服したのは、そのロジカルな文章構成。勿論、山岡氏の新訳によるところも大とは思いますが、バーバラミントの提唱する「ピラミッド原則」「MECE」が既にこの時代に存在しているとさえ思ってしまいました。2014/06/14
Shun
12
時折、英国から見て極東の「日本」に言及も何度かあり、うれしい気分になった(違) この原書が出版されたのが1776年ということなので、日本は安永7年の10代将軍徳川家治の時代。この数年後、寛政の改革などがあり、日本史を思い起こせば、江戸幕府でも物価・通貨政策をやっていたことを考えると、当時の日本でもそれなりに経済研究されていたのだろうか。 自分は空白期間があり、3ヶ月ぐらいかかってしまったのですが、ビジネスしている人は、視野を広くするために、そうで無い人も教養として読む価値ある書籍だと思います。2019/12/23
きゃれら
3
議論は18世紀のイギリスが舞台となっているのだが、中身は今でも十分に通用するものが多い。「政府債務」のところは、イギリス国家の借金が戦争により雪だるま式に増えていく様子を書いた上で、解消する処方箋を示していて、新型コロナにとめどなく歳出する日本に住む者として頭の痛い話だった。流行りのMMTでは国はいくら借金してもよいというけど、それって直感を裏切る話だよなあ。スミスさんは兌換紙幣による事実上の金本位制を前提にしており通貨の形がまるで違ってみえているのだけど。参考書をいろいろ読まないといけない気がする。2021/01/04
\サッカリ~ン/
3
重商主義批判と自由放任主義政策への変換を訴えるのが前半分。スミスの教育および国家観が後半に展開される。当然だが小さな国家(必要最小限の関与)を訴えている。経済に関しては他の人が詳しく分析しているのでここでの言及を避けるが、p348から展開されるスミスの教育に対する思いはなかなかピックアップされないのが残念である。経済の著名人のため仕方ないが、予算や経費に言及するだけでなく、大学システムそのものへの不信感が読み取れる。経済学者としての彼ではなく、哲学的な面としての彼を覗いてみるのも箸休めとしていいだろう。2013/09/08
-
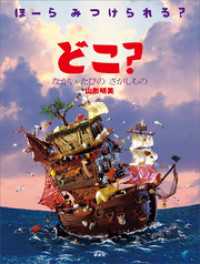
- 電子書籍
- どこ? ながい たびの さがしもの 講…
-
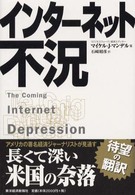
- 和書
- インターネット不況