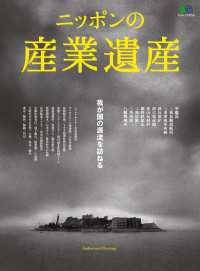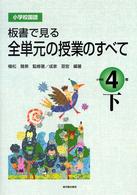内容説明
166点の図とイラストでEVのしくみの「なぜ?」がわかる!
目次
第1章 電気自動車の歴史と変遷
第2章 電気自動車の種類と特徴
第3章 自動車用電池の基礎知識
第4章 電気の基本とモーターの基礎知識
第5章 パワーエレクトロニクスの基礎知識
第6章 電気自動車の充電システム
第7章 電気自動車の将来と課題
著者等紹介
飯塚昭三[イイズカショウゾウ]
1942年東京生まれ。1965年東京電機大学機械工学科卒。同年、自動車・機械関連などの老舗出版社、山海堂に入社し、自動車工学・整備関係の書籍編集に従事した。1969年にモータースポーツ専門誌『オートテクニック』の立ち上げに参画、取材を通じてモータースポーツに関わる一方、自身もレースに多数参戦して、編集者ドライバーの先駆けとなる。編集長を務めた後、87年にジムカーナを主テーマとした『スピードマインド』を創刊し、企画・編集に携わった。2000年にフリーランスに転じ、テクニカルライター・編集者として自動車の技術的な解説記事を執筆している。日本EVクラブ会員。日本自動車研究者ジャーナリスト会議(RJC)前会長。また、一般社団法人日本陸用内燃機関協会の機関誌『LEMA(陸用内燃機関)』の編集長を務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KNJOB
7
知ってること、知らないこと様々だったが、どれも図解があり、著者の優しさを感じる本だった。 一部を掘り下げること。全体を俯瞰すること。 それが技術も環境も考え方も片寄らずに時に浅く広く、時に深く狭くを、行ったり来たりしながらこれからの世の中に向き合って、変化をどう受け止めていくかを感じながら読めた。 読んでいて、安心して読めた。 そう感じる本だった。2022/01/05
Hira S
4
タイトル通りきちんとしている。足元のメカニズムだけでなく、充電規格の変遷、全固体電池と空気金属電池、走りながらのワイヤレス給電といった将来像が技術的に示されている。2021/10/17
まろん
1
★★★☆☆ EVのメカニズムについて、特に電池とモーターに関して図を交えて解説した本。図が多く分かりやすいが、化学屋にとって電磁力の説明は難解だった。勉強する良いきっかけに。:一定電力(電圧×電流)を送る場合、電圧を高めて電流を低めた方が送電ロスが少ない。交流の場合、電圧の上げ下げがコイルを使って簡単にできるうえ、直流にする整流も簡単。コイルとコンデンサは対の特性をもつ。コンデンサは交流を通し、直流を通さない、コイルはその逆。電動モーターの内燃エンジンとの違いは、0回転から最大トルクが発揮される点。2020/05/05
Haruki
1
プリウスに代表されるハイブリッドから始まり、リーフやテスラといったEVまで普及しつつある電気自動車について、そのメカニズムが分かりやすい。電池、インバーターの簡単な構成、モーターの種類(誘導、同期)、充電方式の種類などがざっと一覧できる。 これを読めば記事やサイトに出てくる開発項目の内容が理解できるようになる。もちろん技術の最先端まで理解するには別途学ぶ必要がある。 エンジンとモーターのトルク特性の差、電池の改良、さらにはワイヤレス給電が進むとビジネスモデルとして良い筋になってくるのが面白い点である。2019/12/11