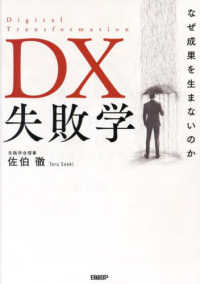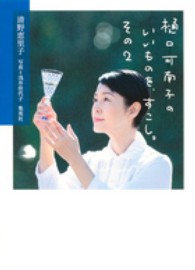目次
第1章 助走―V‐2とその争奪戦
第2章 大統領の号砲―勇気ある決断
第3章 冒険者と匠の対立と接近―マーキュリー
第4章 アポロへの美しい橋―ジェミニ
第5章 慟哭からのスタート―苦悩するアポロ
第6章 史上最高の遠征―冒険者、月へ行く
第7章 嵐の中のアポロ―匠たちの格闘
第8章 語り始める岩石―科学者たちのアポロ
第9章 呼びかけるアポロ
著者等紹介
的川泰宣[マトガワヤスノリ]
1942年(昭和17年)2月23日、広島県呉市生まれ。1965年(昭和40年)東京大学卒業。1970年(昭和45年)東京大学大学院博士課程最後の年に、日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに参加。以後、ハレー彗星探査、科学衛星計画、「はやぶさ」など、数々のロケット開発・衛星開発に携わる。東京大学宇宙航空研究所・宇宙科学研究所・宇宙航空研究開発機構(JAXA)を経て、JAXA名誉教授、はまぎんこども宇宙科学館館長。工学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
89
三つのアポロ、このタイトルはアポロは決して宇宙飛行士だけが作り上げたものではない、技術者と飛行士と科学者の三者が紡いだ「三つのアポロ」という意味。サブタイトルの如くロケットの創世記から有人飛行、マーキュリーやジェミニ計画。月面着陸を実現させた人々のドキュメントだ。アポロ11号の月面着陸ばかりが注目されがちだが11号の前後にアポロとして着陸のシュミレーションや様々な活動を行っていることを忘れがちだ。以前読んだアポロに関する海外の訳本と違い、この本はもとが日本人が書いているので格段に読みやすかった。図書館本 2019/09/01
スプリント
15
ロケット開発をめぐる米ソの熾烈な競争と国家のイデオロギーに振り回される科学者達がとても印象に残りました。 宇宙飛行士は理系なのに体育会系のノリが微笑ましいですね。2019/09/24
ふくみみ
7
3つの、とは技術者と飛行士と科学者を指す。宇宙に勇気を持って飛び出していった飛行士だけでなく,国に対して宇宙計画を説得した科学者、人間が乗って使うために制約の多いロケットやユーザインターフェイスを設計した技術者がいた。関わった科学者がドイツやソビエトで迫害されていたことや、飛行士と技術者のぶつかり合いなど知らないことも多かった。マーガレット•ハミルトンのことはもっと突っ込んで読んでみたいなぁ。2021/03/13
ひで
7
「人間の月面着陸・地球帰還」をアメリカの国家目標として進められた『アポロ計画』。その政治的背景や、技術開発、宇宙飛行士のエピソードが時系列に述べられていて概要をよく理解することができた。ソ連との開発競争に国の威信がかかり、急がれる計画。アポロ11号による人類初の月面着陸・地球帰還。アポロ13号の事故と奇跡の生還くらいしか知らなかったが、アポロ計画以前のロケット開発からNASAの設立なども述べられていて、とても興味が湧いた。他の関連書や映画なども探してみてみたいと思った。2020/07/07
zikisuzuki
5
V2ロケットのフォン・ブラウンとソ連のコリョホフとのライバルで幕を開けた宇宙開発。政治家、ハード及びソフトの技術者、パイロットそして科学者がお互いにリスペクトしあった時に結実したアポロ計画と月面探検。人間達の思いが立ち現われるとても良い読み物だった。特にアポロ計画に入ってからは迫力があった。難しすぎず軽すぎずの良い塩梅、アポロ陰謀説が根強くある現代だけど、その技術や科学の成果をみて素晴らしい快挙の事実だったと分かる。宇宙を見上げて生きて行こうよ。2019/07/27