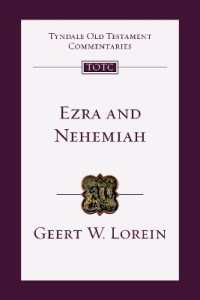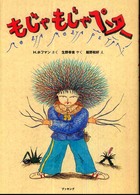出版社内容情報
《内容》 肝臓病教室を開催して10年の著者が,若手医師,看護師,栄養士,保健師などに向けてまとめたテキスト.肝臓病では,病気に対する知識を深めることが患者の高いQOLを得るために不可欠である.本書は,患者教育に携わるスタッフが,患者の疑問に正しく答え,患者の状態に合わせて適切な情報を伝達するために役立つ一冊.患者さんや家族の方にも好適なテキスト.2色刷.
《目次》
【主要目次】
1章 慢性肝臓病とは
1.肝臓の構造と機能
2.肝炎の原因
3.慢性肝炎
4.肝硬変
5.肝がん
6.アルコール性肝障害
7.脂肪肝
8.自己免疫性肝炎
9.原発性胆汁性肝硬変(PBC)
10.薬剤性肝障害
2章 医療面接,症状,身体所見
1.肝臓の訴えを聴く
2.肝臓病の症状
a.易疲労感,倦怠感
b.黄疸
c.皮膚のかゆみ
d.こむら返り
e.腹水,浮腫(むくみ)
f.手掌紅斑
g.くも状血管腫
h.女性化乳房
i.吐血
j.肝性脳症
k.発熱
3.身体所見
a.肝腫大
b.腹水
c.黄疸
3章 肝臓病の検査
1.基準値とは
2.検査のゆれとは
3.血液(尿)検査
a.肝機能検査
b.ウイルス検査
c.腫瘍マーカー
4.画像検査
a.腹部超音波(エコー)検査
b.CT(コンピューター断層)検査
c.MRI(磁気共鳴)検査
d.肝シンチグラフィ
e.血管造影
5.内視鏡検査
a.上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査
b.腹腔鏡検査
6.病理組織検査:肝生検
7.疾患別の検査と診断
a.肝硬変
b.肝がん
c.脂肪肝
4章 肝臓病の治療
1.インターフェロン療法
a.インターフェロン製剤
b.B型慢性肝炎に対するインターフェロン治療
c.C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療
d.インターフェロンの副作用
2.抗ウイルス薬
a.ラミブジン
b.リバビリン
3.肝庇護薬
4.瀉血療法
5.漢方薬
a.小柴胡湯
b.芍薬甘草湯
6.分枝鎖アミノ酸製剤
7.症状別の治療法
a.腹水
b.肝性脳症
c.食道静脈瘤
8.疾患別の治療法
a.肝硬変
b.肝がん
c.アルコール性肝障害
d.脂肪肝
e.自己免疫性肝炎
f.原発性胆汁性肝硬変
5章 肝臓病と日常生活上の注意
1.感染予防対策:他の人に感染させないために
2.ワクチンの接種
3.慢性肝炎および代償期肝硬変の食事療法
a.肝硬変の栄養状態
b.食事療法の進め方
4.積み上げ方式からイメージの改変へ:私の考える栄養指導のあり方
a.今までの栄養指導(積み上げ方式)
b.これからの栄養指導(イメージの改変へ)
5.疾患・症状別の食事療法
a.慢性肝炎や代償期肝硬変の食事
b.肝性脳症のある時期
c.腹水や浮腫(むくみ)のある時期
d.栄養状態の悪い時期
e.食道静脈瘤のある時期
f.糖尿病を合併した場合の食事
6.肝臓病と運動・安静
a.運動指導の対象
b.運動指導の実際
c.ウォーミングアップと継続の重要性
d.許容される運動の強度は
e.運動指導により期待されること
7.肝臓病とアルコール
8.呼吸法
9.睡眠
10.薬剤
a.肝硬変と睡眠薬,消炎鎮痛薬
b.肝硬変と一般薬
11.旅行
12.性生活
肝臓病 QアンドA
巻末付録 肝臓病の献立例(カラー)
索引
内容説明
肝臓病の患者教育を行おうとする人にとって、患者を中心においた肝臓病の知識を理解し整理するために役立つことを、同時に、肝臓病を患いその情報を希求する患者さんにとり、病気を抱えながらも高いQOLを維持した生活を送るためのよき指針となるテキスト。
目次
1章 慢性肝臓病とは
2章 医療面接、症状、身体所見
3章 肝臓病の検査
4章 肝臓病の治療
5章 肝臓病と日常生活上の注意
肝臓病QアンドA
巻末付録 肝臓病の献立例
著者等紹介
加藤真三[カトウシンゾウ]
1980年慶応義塾大学医学部卒業。1985年慶応義塾大学大学院修了。1986~1988年米国ニューヨーク市立大学マウントサイナイ医学部研究員。1990~1993年都立広尾病院内科医長、内視鏡科科長を経て、1996年より慶応義塾大学医学部消化器内科講師、現在に至る。肝臓病の臨床に従事し、アルコール性肝障害を中心に研究を行っている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。