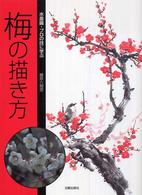内容説明
銀行は、規制業種としての公共性と上場会社としての私企業性の2つの側面をあわせもつため、経営の健全性と投資家の保護のいずれも欠くことはできない。本書の最大のテーマである不良債権処理については、銀行法は条文を置いていないため、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従う」ものとされているが、これだけでは会計処理ができないため、金融当局が詳細な規定を定めてきた。本書では、銀行監査が導入された1976年から2004年までに起こった銀行の不良債権処理の会計・監査の実態について、上記の2つの側面から解明を試みるものである。
目次
第1部 わが国の銀行の不良債権処理の会計・監査(銀行監査導入時の銀行会計;銀行監査の導入;資産の自己査定制度導入までの会計基準の変遷;バブル崩壊後の不良債権処理の会計・監査;資産の自己査定制度の導入;資産の自己査定制度導入時における会計基準の問題点;日本長期信用銀行事件と日本債券信用銀行事件の考察;資産の自己査定制度導入後の会計・開示制度の進展;金融再生プログラムの時代;中小企業金融円滑化法の銀行会計・監査に与える影響)
第2部 米英ならびに国際機関等の見解と動向(米国の銀行の貸倒引当金規制;「発生損失アプローチ」から「予想損失アプローチ」へ;実現しなかったコンバージェンス;英国金融危機における銀行の監査人の判断;バーゼル銀行監督委員会と銀行会計・監査;まとめと展望)
著者等紹介
児嶋隆[コジマタカシ]
1950年愛媛県生まれ。1975年一橋大学商学部卒業。1979年公認会計士登録。1992年米国公認会計士登録(モンタナ州、2000年イリノイ州)。米国公認会計士協会会員登録。朝日新和会計社、パリバ証券会社東京支店、チェース・マンハッタン銀行東京支店、センチュリー監査法人(名称はいずれも勤務当時)、岡山大学助教授、教授を経て、2003年中央大学教授。2010年~2011年シェフィールド大学客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。