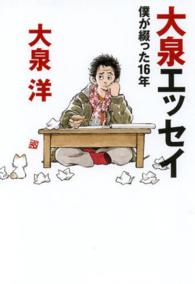出版社内容情報
本書のタイトルは『Linux活用術』,内容を平たく言えばLinuxの上で動く便利なアプリケーションのマニュアルということです。どんなアプリケーションかというと,理工学系の学生が論文を作成する上で便利なものを解説しています。すなわち,とても実用的な内容を含んでいます。実際,数式の美しさでは他の追従を許さないLATEXや,理工学系の論文で必要な体裁のグラフを自由に作成できるGnuplotなどは,ビジネスユーザ-を対象に売られている商用のアプリケーションとは質を異にしてます。そして,この一見異質なアプリケーションの方が『かえって便利ですよ』とも主張したいわけです。
もう一歩踏み込みましょう。
近頃の学生諸君のコンピュータの利用状況を見ると疑問に思えてなりません。WWWのブラウザーでボタンを次々クリックして,まるでテレビをボヤーと見ているだけのようで,『あー,もったいないなぁ』と思ってしまいます。もっと自分の勉強に役に立つ使い方がある筈なのに,どうしてこう受身になっているのでしょう?『そういえば,実習でもテキストに書いてある通りに(ときには明らかな間違い通りに)コマンド(コマンドという意識もないかもしれない)をロボットのように入力していたなぁ』なんて嘆きだけが頭の中を巡ります。
これは偏見かもしれませんが,この受身の使い方は『何も知らないユーザーが直観で操作できるインターフェイス』に踊らされたせいではないかと思います。特に理工学系の学生は,基本的には『何も知らないユーザー』でもあるべきですが,一方,『便利に見せかけるための様々な技術や工夫』を読むセンスを磨かなければいけない筈です。
そして,そのためには,『自分の頭で考えコンピュータという機械に言葉で指示を与えていくのが一番』であると結論されたのです。Linux上の厳選されたアプリケーションは,そのような思考や操作を必要とします。『自分が何をどうしたいのか,そのためにはどうすればいいのか』を常に考えながら,そうしてコンピュータを自分のものにしていって欲しいと願っています。
大袈裟になってしまいましたが,筆者がLinuxを愛用する理由の一つに,『思い込み』をあげることができます。ネットワークを通じてLinuxはいいぞとお互いに感激しあえる幸せを,学生諸君にも教えてあげたい気持ちで一杯です。ぜひLinuxを活用してください。
最後に,ネットワークを通じて,この本の講評を頂いた皆様にお礼申し上げます。特に,山崎康宏氏には内容に深くかかわった指摘を頂きました。また,遅筆を辛抱強く待って頂いた出版局の植村八潮さんと,にこやかな笑顔の松崎真理さんに感謝致します。
1998年10月
松田七美男
1章 はじめに
1.1 LinuxとPC-UNIX
1.2 本書について
2章 設定の色々
2.1 ログインシェル
2.2 Xウィンドウ
2.3 各ツール
3章 エディタ:Mule
3.1 起動画面
3.2 基本操作
3.3 知っていると便利な機能
4章 文書作成:LATEX
4.1 こんにちは,LATEX
4.2 仕上がりの確認:Xdvi
4.3 LATEXコマンド概要
4.4 入力支援ツール『野鳥』
4.5 PostScriptファイルの扱い
4.6 理工学系論文のためのTips
4.7 化学式
4.8 図に関して
4.9 プログラムのソース
4.10 OHP原稿作成
4.11 その他
5章 グラフ作成:Gnuplot
5.1 対話的な使い方
5.2 二次元プロット:plot
5.3 式
5.4 オプションの設定:set option
5.5 データ(点列)の表示
5.6 多彩な出力形式の利用
5.7 三次元プロット:splot
5.8 非対話的な使い方:スクリプトで制御
5.9 媒介変数表示:set parametric
5.10 極座標表示:set polar
5.11 バージョン3.6の注目すべき新機能
5.12 繰返し:reread
5.13 Gnuplotの大技小技
5.14 gnuplot+
5.15 Emacsとの連携
5.16 他のプロットツール
6章 ドローイング:Tgif
6.1 Tgifの起動
6.2 機能の呼出し:メニュー
6.3 日本語の入力
6.4 キー入力コマンド
6.5 他のツールとの連携
6.6 テクニックの上達
6.7 図面集
索引
内容説明
本書は、Linux上で動く便利なアプリケーションで、理工学系の学生が論文を作成する上で便利なものを解説しました。
目次
1章 はじめに
2章 設定の色々
3章 エディタ:Mule
4章 文書処理:LATEX
5章 グラフ作成:Gnuplot
6章 ドローイング:Tgif
-
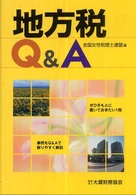
- 和書
- 地方税Q&A