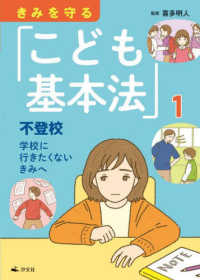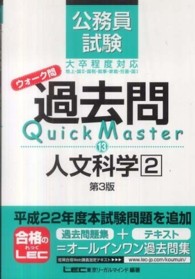出版社内容情報
《内容》 本書は輸液に必要とされる知識のキーポイント,データ,処方例などを簡潔にまとめたベッドサイドメモである.体液生理学・栄養生理学・体液電解質異常の症候と検査,病態と治療指針・輸液療法の進め方・輸液剤の種類と特徴・栄養輸液の実際・主要な病態,疾患における要点にわたって実践のためのノウハウをコンパクトに収めた. 序 輸液療法は現在では,日常の臨床において,どの科においてもごく普遍的な治療法の一つになっている.輸液療法は大きく水電解質の治療法と栄養管理法に区別することができる.この体液管理と栄養補給は生体の恒常性を維持する上で最も基本的なことであり,どのような病態や疾患においても必要不可欠な事項であるといえる. ところが,輸液治療法というのは難しいといわれたり,逆にそれ程気にしなくても簡単に行われるというような相反する考え方があるようである.体液代謝というものを厳密に考えると,確かに不確定な事柄が多く,また用語の複雑さや調節系についての膨大な知識を理解するという点からは困難な面が少なくない.しかし,このような輸液療法は腎臓の機能に依存した治療法であるために,腎機能がそれ程障害されていなければ,よほどの間違った治療方針でない限り,生体には害悪は及ぼさないともいえる.このため安易に輸液療法が行われることにもなるわけである. 輸液療法は緊急的な治療法である一方,きわめて日常的な維持治療法でもある.輸液の目的により治療法の困難さや厳密さが異なることになる.しかし,いくら厳密に計算式や投与量などを設定しても,不確定な因子は常に存在するものであり,一見きわめて科学的に見える治療法にもブラックボックスが存在するのである.しかしながら,このような事実があっても,できる限り体液代謝に則った方針で実施するのが本道である. 臨床経験の豊富な場合には,このような輸液治療は今までの経験的な方針により問題なく行われているかもしれないが,手元に参考書があれば必要に応じて参照する必要性は常に存在する.臨床経験の浅い場合には,先輩の方針にしたがって,盲目的に追従することが多いかもしれない.しかし,どのような意味で輸液治療が行われているのかを,常に自問自答することは大切なことであると考えられる. 本書ではこのような点から,必要に応じて参考とする知識を備忘録的にまとめたものであり,臨床の場で活用していただくために図表を中心に簡略化した.このため輸液治療法について初めて学習する読者には難解な面が少なくないが,これは他の輸液の書物により基礎から学習して頂きたい.本書の活用法は,あくまでも知識を整理するという利用の仕方をお勧めする. 最後に本書を著すに当たって参考とさせていただいた書物を一覧し,謝辞を述べたいと思う.先駆的なこれらの書物は,著者自身も勉強させていただいた書物であり,長い年月を生き抜いてきた名著の誉れ高い書物が多いのである.これらの書物以外にも,医学雑誌には電解質,輸液療法の特集記事が適宜編集されるが,これらの内容についても参考にした部分が少なくない.そのままの形で引用することは避けたが,内容についての誤記があれば,すべて著者の責任であり,これらの参考図書には責任はない. 改めてこれらの参考図書に感謝するとともに,本書では内容不足の場合にはこれらの図書を参照していただきたい. 越川昭三:輸液,中外医学社 森岡恭彦,齋藤英昭:外科栄養・代謝管理ハンドブック,中学医学社 1995年1月 北岡建樹 《目次》 目次 I.輸液療法の基本的知識 1 A.体液生理学 1.体液量の区分 2 2.体液の量,分布に影響する因子 3 3.体液区分における電解質組成 4 4.浸透圧(1) 5 5.浸透圧(2) 6 6.膠質浸透圧 7 7.STARLINGの法則 8 8.DONNANの平衡 9 9.体液量の調節機構 10 10.レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系 11 11.体液量の調節に関係する因子 12 12.水分の摂取と排泄のバランス 13 13.体液のバランス 14 14.不感蒸泄と発汗(成人) 15 15.消化液中の電解質組成(平均値) 16 16.Naの体内分布と代謝 17 17.Clの体内分布と代謝 18 18.Kの体内分布とその代謝 19 19.細胞内外のK移動調節因子 20 20.腎におけるK排泄の調節因子 21 21.H+の調節系 酸排泄機構 22 22.Caの体内分布と調節系 24 23.Ca代謝の調節機構(低Ca血症時) 25 B.栄養生理学 1.糖質の分類 26 2.糖質の代謝経路 27 3.脂質の分類 28 4.解糖系(EMBDEN-MEYERHOFの経路) 29 5.TCAサイクル(クエン酸回路・クレブス回路) 30 6.乳酸の代謝経路 31 7.タンパク質(アミノ酸) 32 8.アミノ酸の分解と代謝 33 9.尿素サイクル(オルニチンサイクル) 34 10.窒素平衡(Nバランス) 35 11.Nバランスの求め方 36 12.微量元素の特徴 37 13.ビタミンの特徴 38 II.体液,電解質異常の症候と検査 41 1.水-電解質異常の診療方針 42 2.身体所見のみかた 43 3.バランスシート 44 4.体液電解質異常の原因となる症候 45 5.体液電解質異常の原因となる主要疾患 46 6.電解質異常の原因となる薬物 47 7.抗生物質の中のNa含量 48 8.電解質異常による症候 49 9.尿量の異常 50 10.乏尿の原因 51 11.乏尿の鑑別法 52 12.多尿の原因 53 13.多尿の鑑別法 54 14.体液電解質異常の検査法 55 15.電解質と単位 56 16.mEq/l, mOsmの計算法 57 17.血清電解質,血漿浸透圧の正常値 58 18.血漿浸透圧の異常 59 19.オスモラールギャップ 60 20.アニオンギャップ 61 21.尿中電解質の測定と解釈 62 22.尿アニオンギャップ 63 23.尿アニオンギャップの応用 64 24.尿pHの評価 65 25.体液量の測定法 66 III.体液,電解質異常の病態と治療指針 67 A.体液量の異常 脱水症と浮腫 1.脱水症の原因と分類 68 2.体液量欠乏の病態 69 3.水分欠乏型脱水症とNa欠乏型脱水症の比較 70 4.体液量欠乏の程度 71 5.水分欠乏量の求め方 72 6.水分欠乏量の推定法 73 7.Na欠乏量の求め方 74 8.脱水症の一般的治療方針 75 9.溢水overhydrationの種類 76 10.体液量過剰の症候と検査 77 11.浮腫の診療の進め方 78 12.浮腫の原因 79 13.浮腫発生の局所性因子 80 14.主要な全身性浮腫の鑑別 81 15.心不全の浮腫発生機構 82 16.肝硬変症の浮腫,腹水発生機構 83 17.浮腫の治療方針(1) 84 18.浮腫の治療方針(2) 86 19.浮腫の一般的な治療指針 88 20.利尿薬の種類 89 21.利尿薬の種類と作用部位 90 22.利尿薬の主な副作用 91 23.主要利尿薬の特徴 92 24.利尿薬の副作用とその対策 94 B.血清Na濃度の異常 高Na血症と低Na血症の診断と治療 1.血漿浸透圧と体液量の関係 95 2.血清Na濃度の異常 高Na血症 96 3.血清Na濃度の異常 低Na血症 97 4.高Na血症の原因 98 5.高Na血症の鑑別法 99 6.高Na血症の治療方針(1) 100 7.高Na血症(水分欠乏症)の治療方針(2) 101 8.低Na血症の鑑別法 102 9.低Na血症の原因 104 10.低Na血症の治療方針 105 11.低Na血症(Na欠乏型)の治療指針 106 12.低Na血症(Na希釈型)の治療指針 108 13.低Na血症(浮腫型)の治療指針 109 C.血清K濃度の異常 高K血症と低K血症の診断と治療 1.血清K濃度と体内K量 110 2.高K血症の原因 111 3.高K血症の鑑別法 112 4.高K血症の診療手順 113 5.血清K濃度と心電図所見 114 6.高K血症の緊急治療法 116 7.重症高K血症の治療方針 118 8.低K血症の原因 120 9.血清K濃度異常の症候比較 121 10.低K血症の鑑別法 122 11.K欠乏量の求め方 124 12.低K血症の治療方針 125 13.低K血症の治療法 126 D.血清Cl濃度の異常 1.血清Cl濃度の異常 127 2.低Cl血症の治療方針 128 3.高Cl血症の治療方針 129 E.酸塩基平衡異常 診断と治療 1.酸塩基平衡の概念 130 2.体内における酸塩基平衡の調節系 131 3.酸塩基平衡の異常(単純性) 132 4.代謝性アシドーシスの原因 133 5.代謝性アシドーシスの鑑別(単純性) 134 6.代謝性アシドーシスの治療方針 135 7.代謝性アシドーシスの治療法 136 8.HCO3欠乏量の求め方 138 9.乳酸性アシドーシスの治療方針 139 10.代謝性アシドーシスの鑑別と治療法 140 11.代謝性アルカローシスの原因 142 12.代謝性アルカローシスの鑑別(単純性) 143 13.代謝性アルカローシスの鑑別と治療方針 144 14.呼吸性酸塩基平衡障害の原因と検査所見 146 15.呼吸性酸塩基平衡異常の原因 147 16.呼吸性アシドーシスの治療方針 148 17.呼吸性アルカローシスの治療方針 149 18.SIGGARD ANDERSONノモグラム 150 19.単純性酸塩基平衡異常の代償反応 151 20.混合性酸塩基平衡異常の原因 152 21.酸塩基平衡異常の治療方針 153 F.Ca, Mg, P代謝異常 診断と治療 1.Caの補正式 154 2.高Ca血症と低Ca血症の原因 155 3.高Ca血症と低Ca血症の症候 156 4.高Ca血症の原因 157 5.高Ca血症の鑑別法 158 6.高Ca血症の治療法 160 7.高Ca血症の治療方針 162 8.血清Ca濃度異常の治療方針 163 9.低Ca血症の鑑別法 164 10.低Ca血症の治療法 166 11.血清P濃度の異常 168 12.慢性低P血症症候群 169 13.低P血症の治療法 170 14.高P血症の治療 171 15.高Mg血症と低Mg血症の診断と治療 172 IV.輸液療法の実際 173 A.輸液療法の進め方 1.輸液の目的と適応 174 2.輸液の種類 175 3.輸液療法の計画 176 4.維持輸液療法 177 5.食事と維持輸液法の比較 178 6.通常の維持輸液療法の組み立て方 180 7.輸液量の決定の方針 182 8.輸液量の決定 184 9.欠乏量のある場合の輸液剤選択 186 10.通常の維持輸液剤の選択 187 11.1日必要量(成人) 188 12.正常腎における安全限界の概念 189 13.輸液の安全限界 190 14.輸液の副作用 191 15.輸液剤の一般的投与速度,投与量 192 16.輸液治療モニター 194 B.輸液剤 種類と特徴 1.輸液剤の分類 195 2.輸液剤の種類と組成(理論値) 196 3.単純電解質輸液剤(1) 198 4.単純電解質輸液剤(2) 200 5.単純電解質輸液剤(3) 202 6.糖質輸液剤 204 7.複合電解質輸液剤の適応と特徴 206 8.脂肪輸液剤 207 9.アミノ酸製剤 208 10.糖加アミノ酸製剤 210 11.血漿増量剤 211 12.浸透圧輸液剤 212 13.輸液剤による合併症(1) 213 14.輸液剤による合併症(2) 214 V.栄養輸液療法の実際(経腸栄養を含む) 215 1.摂取熱量の程度 216 2.必要熱量の決め方 217 3.必要栄養成分 218 4.栄養管理法の選択 219 5.輸液の手順 220 6.経腸栄養法 222 7.経腸栄養食品(剤)の種類と特徴 223 8.経腸栄養剤 224 9.経静脈栄養法 225 10.末梢静脈栄養法 226 11.末梢静脈栄養法の点滴システム 227 12.中心静脈栄養法の適応 228 13.中心静脈カテーテル挿入 229 14.中心静脈栄養法(IVH) 230 15.高熱量輸液時の血糖管理 231 16.高熱量輸液用の市販基本液 232 17.脂肪輸液剤 234 18.必須脂肪酸欠乏症状および代謝障害 235 19.脂肪過重症候群 236 20.アミノ酸製剤の投与 237 21.アミノ酸製剤の窒素比 238 22.アミノ酸輸液剤のNa, Cl濃度 239 23.市販総合ビタミン剤(高熱量栄養輸液用) 240 24.ビタミン,微量元素の投与量(成人) 241 25.高熱量輸液処方例 242 26.高栄養輸液の投与量 244 27.特殊病態における高熱量輸液例 245 28.高熱量輸液中の管理モニタリング 246 29.栄養評価法の手順 248 30.栄養管理モニター 250 31.栄養評価法のチェック項目 252 32.高熱量輸液の副作用 253 33.高熱量輸液の副作用の対策(1) 254 34.高熱量輸液の副作用の対策(2) 255 35.血漿製剤使用のガイドライン 256 36.アルブミン製剤の使い方 257 VI.重要疾患における輸液療法 259 1.緊急,救急輸液法 260 2.ショックの種類 261 3.ショックの病態 262 4.ショックにおける対策と必要な検査 263 5.ショックに対する輸液療法 264 6.ショック対策の目標値 266 7.カテコールアミン系昇圧剤の種類 267 8.出血性ショックの重症度 268 9.意識障害時の輸液 269 10.意識障害の原因と対策 270 11.脳卒中の輸液指針 272 12.意識障害の分類(3-3-9度方式) 274 13.脱水症の輸液指針 275 14.大量嘔吐の病態 276 15.嘔吐の治療 277 16.高度下痢の病態 278 17.嘔吐・下痢による体液異常の治療方針 279 18.うっ血性心不全の原因と病態 280 19.FORRESTERの分類による 心不全の病態と治療方針 281 20.心不全における輸液法 282 21.慢性心不全の病態 283 22.肝硬変の輸液療法 284 23.肝不全の治療方針 286 24.乳酸性アシドーシス 288 25.乳酸性アシドーシスの治療 289 26.急性腎不全(乏尿性) 290 27.急性腎不全の鑑別 291 28.慢性腎不全の治療指針 292 29.腎不全の輸液療法の原則 294 30.ネフローゼ症候群の原因と病態 295 31.ネフローゼ症候群の治療方針 296 32.糖尿病にみられる体液電解質異常 298 33.糖尿病性ケトアシドーシスと 高浸透圧性非ケトン性昏睡 299 34.糖尿病患者の昏睡鑑別診断 300 35.糖尿病性ケトアシドーシス(DKA) 302 36.糖尿病性ケトアシドーシスの治療法 304 37.非ケトン性高浸透圧性昏睡の病態 305 38.非ケトン性高浸透圧血症性昏睡の治療法 306 39.低血糖性昏睡の治療法 307 40.高齢者に体液異常の出現しやすい理由 308 41.加齢による体液成分比と腎機能の変化 309 42.高齢者の体液異常の特徴 310 43.高齢者への輸液の特殊性 311 44.小児における輸液の特殊性 312 45.小児脱水症の輸液療法 313 46.熱傷の重症度 314 47.熱傷の程度と範囲 315 48.熱傷の病態(受傷後6~18時間) 316 49.熱傷の輸液法公式 317 50.広範囲熱傷に対するHLS輸液 318 51.悪液質の対策 319 52.手術による体液量の影響 320 索引 322