内容説明
物語としての『三国志演義』は、いかに作られたのか。正史『三国志』に基づいた史実と、フィクションを交えた叙述のスタイルを分析する。さらに唐代以前から明清代にいたる『演義』の成立事情、謎につつまれた作者羅貫中の人物像、関羽・劉備・張飛ら登場人物のキャラクターの変遷など、奥深い作品世界を案内する。後半では、『演義』の研究にも大きな影響を与えた民間伝承『花関索伝』、明清代の書坊による出版戦争、『演義』に反映された正統論や五行思想など、物語の背後にある文化や世界観も描き出す。本「増補版」では、初版から十七年を経た研究の進展を随所に反映させるとともに、日本と韓国における『演義』受容の様相を第九章として新たに加えた。
目次
1 物語は「三」からはじまる
2 『三国志』と『三国志演義』―歴史と小説
3 『三国志』から『三国志演義』へ―歴史から小説へ
4 羅貫中の謎
5 人物像の変遷
6 三国志外伝―『花関索伝』
7 『三国志演義』の出版戦争
8 『三国志演義』の思想
9 東アジアの『三国志演義』
著者等紹介
金文京[キンブンキョウ]
1952年東京都生まれ。京都大学大学院中国語学文学科博士課程修了。現在、京都大学人文科学研究所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
20
『三国志演義』の概説書。史書との違いはもとより、民間伝承の取り込みや演劇、講談との関係など、書物としての「三国志」の来歴がよくまとまっている。また東アジアでの受容のされ方も増補されており、冊封関係による微妙な政治的陰影を隠せない朝鮮での在り方と、娯楽作品としてリライトされ楽しまれてきた日本での扱いの違いは興味深いところ。関帝信仰の広がりや正統論へのこだわりなど、三国志が単なる歴史書・娯楽作品にとどまらず、東アジア全体の共通文化として大きな存在を占めていることがよくわかる。面白い一冊。2023/02/15
ひよピパパ
15
中国文学研究の第一人者の金文京氏による『三国志演義』に関する概論書。特に勉強になったのは以下の諸点。①歴史と小説の実と虚の問題。特に赤壁の戦いの場面の考証が面白い。実と虚の織り交ぜ方が見事。②『三国志演義』が形成されていく背景。民間で行われていた芸能や語りとの関わりが詳細に説明される。書誌学的説明も詳しい。③作者羅貫中や架空人物関索の秘密。関索に着目するだけでも『三国志演義』の見え方が変わりそう。④『三国志演義』の持つ思想。前提になっているのは蜀を正統とする朱子の『通鑑綱目』。三国志ファン必見の一書!2022/11/28
しゅー
10
★★『三国志演義』の成り立ちを解き明かす本。民衆の語りの中で成立していった講談調の『水滸伝』や、完全にフィクションしている『西遊記』と比べると、『三国志』は今で言う歴史小説っぽい。ただし蜀を正統とするくらいは脚色の範囲だけど、孟獲のくだりみたいに急にお伽噺になったりもして統一感がない(それが楽しいんだけど♪)。また、神格化されすぎた「軍師孔明」とか、本当に神様になってしまった関羽様とか、史実とかけ離れた姿になっていった人物たちがなぜそうなったのか。全部の疑問に答えてはくれないけど楽しく読める学術書でした。2024/02/01
河イルカ
3
同じ著者による講談社の[中国の歴史04]が演義と正史の関係がメインなのに対して、こちらは演義と民間伝承の関係がメイン。特に花関索伝について詳しい。 民間伝承についてここまで詳細な本は、一般的な解説書としては中々ないのではないか。 民間伝承に関する本が少なくて情報不足だったので非常に勉強になった。 これから研究が進んで、正史と演義との間で鼎立してくれるといいのだが。2024/06/13
おきゅーん
2
テキストの研究、キャラクターの研究、etc…何にせよ三国志の研究をするならまずこれを読んでから!という感じです。三国志研究入門と併せて購入をおすすめします。2011/10/18
-
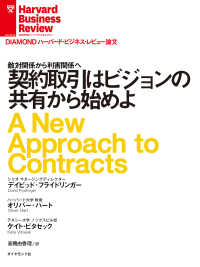
- 電子書籍
- 契約取引はビジョンの共有から始めよ D…
-
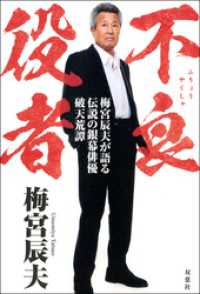
- 電子書籍
- 不良役者 梅宮辰夫が語る伝説の銀幕俳優…







