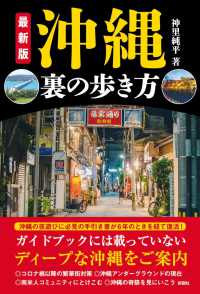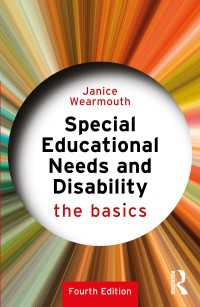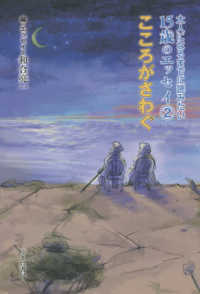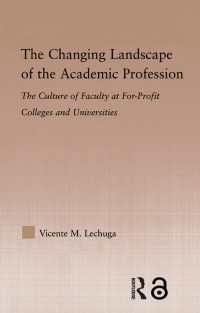出版社内容情報
なぜ、同じような業界・経営環境でありながら、繁栄する企業と破綻する企業に分かれてしまうのか?
なぜ、衰退を認識していながら、破綻に至るまでそこから脱却できなかったのか?
破綻する日本企業には「衰退のメカニズム」が存在する。通常は大きな問題を引き起こすことはないし、見過ごしてしまうことが大半である。しかし、ひとたび事業環境が変化をすると、突然牙をむき始めて、ズルズルと業績を下げ、企業を破綻に追いやってしまう、いわば「サイレントキラー」である。具体的には、ミドルによる社内調整、出世条件と経営陣登用、経営陣の資質と意思決定……、といったことが、企業の業績の成否を分けている。御社にはこのサイレントキラーが眠っていないだろうか。また、サイレントキラーの駆動を避けるには、何をすべきだろうか。企業再生の最前線で活躍してきた著者が膨大な現場の生の声と、経営学・心理学の知見から紡ぎ出した経営組織論のフロンティア。
内容説明
破綻企業と優良企業への膨大なインタビューからあぶり出される企業の実像とは?そして、崩壊を食い止めるためには何が必要なのか?ミドルによる社内調整、出世条件と経営陣登用、経営陣の資質と意思決定…あの破綻した企業たちには、共通する社内メカニズムがあった!産業再生の最前線で活躍してきた著者が現場の声と経営学・心理学の知見から紡ぎ出した経営組織論のフロンティア。
目次
序章 破綻企業に共通する「衰退の法則」をあぶり出す
第1章 破綻企業の内側
第2章 日本企業への文化の影響
第3章 優良企業の内側
第4章 オーナー系企業の内側
終章 日本企業への警鐘
著者等紹介
小城武彦[オギタケヒコ]
1961年東京都生まれ。1984年東京大学法学部卒業、通商産業省(現・経済産業省)入省。1991年プリンストン大学ウッドローウィルソン大学院修了(国際関係論専攻)。1997年カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社、代表取締役常務などを経て、2004年株式会社産業再生機構入社、カネボウ株式会社代表執行役社長(出向)。2007年丸善株式会社(現・丸善CHIホールディングス株式会社)代表取締役社長を経て、2015年より株式会社日本人材機構代表取締役社長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
速読おやじ
mazda
kakoboo
aiken