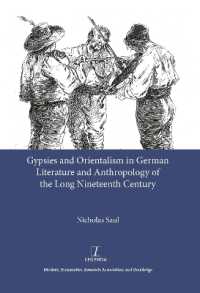出版社内容情報
東京大空襲の記憶や大蔵省勤務時代など、著者の体験談も絡めた戦後日本経済史。日本の病理は残存する戦時経済体制にあると説く。
著者が自らの体験談を豊富に織り交ぜて戦後史を語った、異色の経済書。
日本経済の変貌が著者個人の視点と経済学者としての大きな視点の両方から描かれます。
最初の記憶は、4歳のときに遭遇した東京大空襲。
戦後復興期に過ごした少年時代、1964年の大蔵省入省、アメリカ留学、そして80年代のバブル、90年代・2000年代のグローバリゼーション--。
日本経済は、ダイナミックな成長と成熟を遂げる半面で、
経済思想や政策手段の中に、戦時経済体制的なものをいまだに残している、と著者は指摘します。
戦後70年を迎え、日本経済を改めて理解するための必読書です。
はじめに
戦後を振り返るための年表
プロローグ
第1章 戦時体制が戦後に生き残る 1945-1959
第2章 なぜ高度成長ができたか? 1960-1970
第3章 企業一家が石油ショックに勝った 1971-1979
第4章 金ぴかの80年代 1980-1989
第5章 バブルも40年体制も崩壊した 1990-1999
第6章 世界は日本を置き去りにして進んだ 1980-
エピローグ--われわれがいまなすべきは何か?
おわりに 「頭の中にある40年体制」を克服できるか
【著者紹介】
野口 悠紀雄(ノグチ ユキオ)
早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問
1940年東京生まれ。63年東京大学工学部卒業。64年大蔵省入省。72年イェール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを経て2011年4月より早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問。専攻はファイナンス理論、日本経済論。
主要著書『情報の経済理論』(東洋経済新報社、1974年、日経・経済図書文化賞)、『財政危機の構造』(東洋経済新報社、1980年、サントリー学芸賞)、『土地の経済学』(日本経済新聞社、1989年、東京海上各務財団優秀図書賞、日本不動産学会賞)、『バブルの経済学』(日本経済新聞社、1992年、吉野作造賞)、『経済危機のルーツ』『1940年体制(増補版)』(東洋経済新報社、2010年)、『金融政策の死』(日本経済新聞出版社、2014年)、『1500万人の働き手が消える2040年問題』(ダイヤモンド社、2015年)
内容説明
日本は戦後レジームに回帰しようとしている!東京大空襲からアベノミクスまで、戦後70年をリアルタイムで生きた経済学者の集大成。戦後史を振り返るための年表付き。
目次
第1章 戦時体制が戦後に生き残る―1945‐1959
第2章 なぜ高度成長ができたか?―1960‐1970
第3章 企業一家が石油ショックに勝った―1971‐1979
第4章 金ぴかの80年代―1980‐1989
第5章 バブルも40年体制も崩壊した―1990‐1999
第6章 世界は日本を置き去りにして進んだ―1980‐
著者等紹介
野口悠紀雄[ノグチユキオ]
1940年東京生まれ。63年東京大学工学部卒業。64年大蔵省入省。72年イェール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを経て2011年4月より早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問。専攻はファイナンス理論、日本経済論。主要著書『情報の経済理論』(東洋経済新報社、1974年、日経・経済図書文化賞)、『財政危機の構造』(東洋経済新報社、1980年、サントリー学芸賞)、『土地の経済学』(日本経済新聞社、1989年、東京海上各務財団優秀図書賞、日本不動産学会賞)、『バブルの経済学』(日本経済新聞社、1992年、吉野作造賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
楽
たばかるB
Francis
cape





![マグネットさかなつりずかん あそんでまなべる! [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/43238/4323890818.jpg)