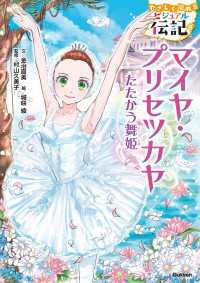出版社内容情報
アベノミクスの経済政策から地域経済の活性化策まで、日本経済のトピックスを「マクロ経済学」にもとづき解説した大人のための教養書
経済の長期停滞、人口減少、少子高齢化、・・・・
日本をとりまく厳しい現実は、経済学の言葉で語るとどんなふうに語れるのだろう。
そして、アベノミクスの経済政策は、どのようなリクツで、この厳しい現状から日本を立ち直らせようとしているのだろう。
断片的情報でいっぱいになってしまったアタマを、「経済学」という縦糸ですっきり読み解いてみよう。すると、今話題の成長戦略はどこに、どのような経路で効いてくるのか、こないのかが自分で判断できるようになる。
成功するか、失敗するか、というようなおおざっぱな議論ではなく、1つ1つの打つ手が、何を目的にしたものなのか、経済学的にはどのように読み解けるのか、を自分で考えるための手引きとなる本。
序章 アベノミクスの経済政策
第1章 バブル経済の発生と崩壊、そして「失われた二〇年」
第2章 金融制度の発展――自由化と危機
第3章 異次元緩和策と伝統的金融政策
第4章 金融市場の一般均衡分析――トービンの金融理論
第5章 金融市場と非対称情報――スティグリッツの金融理論
第6章 成長戦略とサプライサイド経済学
第7章 成長戦略と企業投資
第8章 コーポレート・ガバナンスとM&A
第9章 地域経済と中小企業の活性化
終章 グローバリゼーションとアベノミクス
【著者紹介】
藪下 史郎(ヤブシタ シロウ)
早稲田大学名誉教授
早稲田大学政治経済学術院名誉教授。1943年兵庫県生まれ、1966年東京大学経済学部卒業、1972年イェール大学Ph.D.取得後、東京都立大学(現・首都大学東京)、横浜国立大学を経て、1991年から早稲田大学政治経済学部教授、2014年3月退職。専門は応用マクロ経済学、金融論。イェール大学大学院在籍時にジェームズ・トービン、ジョセフ・E・スティグリッツらに師事。
主な著書に『金融システムと情報の理論』(東京大学出版会、1995年);『金融論』(ミネルヴァ書房、2009年);『貨幣金融制度と経済発展』(有斐閣、2001年);『非対称情報の経済学』(光文社新書、2002年);『中小企業金融入門(第2版)』(共編著、東洋経済新報社、2006年);『スティグリッツの経済学 「見えざる手」など存在しない』(東洋経済新報社、2013年)。訳書に『スティグリッツ 入門経済学(第4版)』(共訳、東洋経済新報社、2014年)などのスティグリッツの一連の経済学教科書のほか、『トービン 金融論』(共訳、東洋経済新報社、2003年)がある。
内容説明
経済の長期停滞、人口減少、少子高齢化といった日本をとりまく厳しい現実、そして、アベノミクスと呼ばれる政策パッケージから次々に繰り出されるさまざまな政策…これらは経済学の言葉で読み解くと、どんなふうに描けるのだろうか。刻々と変わる経済の状況を、そしてさまざまに繰り出される「政策」がどのような可能性を秘めているのかを、自分のアタマで考えるための、手引きとなる本。
目次
アベノミクスの経済政策
バブル経済の発生と崩壊、そして「失われた二〇年」
金融制度の発展―自由化と危機
異次元緩和策と伝統的金融政策
金融市場の一般均衡分析―トービンの金融理論
金融市場と非対称情報―スティグリッツの金融理論
成長戦略とサプライサイド経済学
成長戦略と企業投資
コーポレート・ガバナンスとM&A
地域経済と中小企業の活性化
グローバリゼーションとアベノミクス
著者等紹介
藪下史郎[ヤブシタシロウ]
早稲田大学政治経済学術院名誉教授。1943年兵庫県生まれ、1966年東京大学経済学部卒業、1972年イェール大学Ph.D.取得後、東京都立大学(現・首都大学東京)、横浜国立大学を経て、1991年から早稲田大学政治経済学部教授、2014年3月退職。専門は応用マクロ経済学、金融論。イェール大学大学院在籍時にジェームズ・トービン、ジョセフ・E・スティグリッツらに師事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。