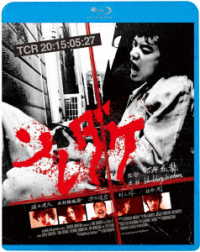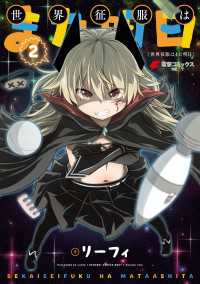出版社内容情報
大学院に進まなくても研究はできるし学会にも所属できる。仕事上研究が必要な人や趣味として研究をやりたい人に贈る、誰にでもできる研究者への道を説く本。
内容説明
現代はすべての人に知的・研究的生活を要求している。誰にでもできる「研究的生活」のガイドブック。
目次
0章 『大学教授になる方法』がなぜ読まれたか
1章 書斎studyがほしかった
2章 ノートパソコン1台で、動く書斎ができる
3章 知的生活社会でどう生きるか
4章 本業としての研究的生活
5章 生きる楽しみとしての研究的生活
6章 生きる励みとなる研究的生活
7章 知的生活の中核に研究的生活をおこう
8章 留学のすすめ、留学の疑問
9章 研究的生活に「老後」はない
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
_udoppi_
1
研究的生活とは知性を尊重し知性に対し誠実に生きることくらいの意味であり、研究生活(学者などの本業としての研究)とは概念を分けている。フンフン頷きながら一瞬で読み終わってしまった。研究的生活は楽しいが仕事として課せられると辛いなんていうのはほとんど本音だろうと思う。コピー可能で普遍的な能力としての「技術」と、しばしば美的価値を伴う一子相伝的な能力としての「芸術」について論じている所は面白かった。8章で留学について述べているが、まったくその通りで、語学能力は論ずる内容があって初めて活きるものだと思う。2011/10/30
Humbaba
1
現在は昔と比べて自分の考えを発表できる環境が整っている.インターネットを利用すれば,簡単に同じ研究を行なっている仲間を見つけることができる.自分の興味が有ることを調べて,そして話し合う.それができるということは,何よりも幸せな生き方といえるだろう.2011/08/30
おらひらお
1
1999年初版。購入後、仕事や勉強、研究などに対するモチベーションが低下したときに、たびたび読み返す本。書いていることは至極もっともなことであるが、はっきり書いているところが良い。今は特に下がっているわけではないが、ぱらぱら読んでみると意欲が涌いたような気がした・・・。2011/02/20
yamayuuri
0
1996年、PCの普及前に書かれたものだからか、ちょっとPCの章が古い気がする。が、研究生活こそ現代人の生涯学習であり、張りになりうることは今も同じか。この本で言ってるのは本業でない研究ですが2010/05/09
きぬりん
0
大学教授のようにそれを本業とするのではなくとも、「研究し調査することが自己目的となるような生き方」、すなわち著者の言う「研究的生活」が、PCやネットワークの普及によりかなり容易になっている現状と、その魅力を伝える。日本における研究的生活の系譜を、古くは漱石や雪嶺に辿り、梅棹忠夫・渡部昇一による知的生産・知的生活ブームを知的生産の技術化・方法化=大衆化とみなし、『「超」勉強法』をパソコンを通じた研究的生活の本格的な幕開けに位置付ける、0章の分析が出色。以後の章は比較的とりとめのない叙述が続き、残念な印象。2022/03/20


![&Premium(アンド プレミアム) 2025年1月号 [カフェと音楽。]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1952714.jpg)