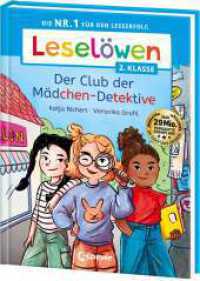出版社内容情報
ウェルビーイング”がわからないままでは、子どもを未来に送り出せない。
次期学習指導要領とも深く関わる、いま押さえておくべきキーワード。
基礎的な理解から、具体的に授業に落とし込んだウェルビーイングの教育”の完全ガイド。
「I」「WE」「SOCIETY」「UNIVERSE」――4つの視点で育む“ウェルビーイング・コンピテンシー”を解説。
■本書の概要
“ウェルビーイングの学び”を、主に学校という学びの現場にどのように取り入れることができるのか、児童生徒の「ウェルビーイング・コンピテンシー」をどのように育むことができるのか、そのための考え方を提案するとともに、具体的な実践方法を併せて紹介します。
■本書からわかること
・次期学習指導要領とも深く関わる、いま押さえておくべきキーワード
文部科学省の「第4期 教育振興基本計画」(2023年6月16日 閣議決定)では、その大きなコンセプトとして「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が掲げられています。
これからの日本の教育において、ウェルビーイングもしくは、それに基づく考え方は、授業設計の指針や評価の観点として重要なテーマの一つになり得ると考えられます。
今現在、確実に押さえておくべきテーマをわかりやすく、教育現場での事例を交えて解説します。まさに教育におけるウェルビーイングの決定版です。
・豊富な実践事例
ウェルビーイングについて理解するだけではなく、実際に学校現場での実践事例をご紹介します。その実践は、「ターゲット型実践」「アレンジ型実践」「WBコンピテンシー振り返りの実践」の3つに分けられます。
<ターゲット型実践>
ウェルビーイングを主たる学習目標とし、それに特化した実践
<アレンジ型実践>
各教科の目標や内容を踏まえた上で、無理なくウェルビーイングを取り入れた実践
<WBコンピテンシー振り返りの実践>
実践効果を児童生徒が自ら振り返り、今後の学習を見通す方法を解説します。評価内容と測定のタイミングを定めたり、カリキュラムの設計方法をご紹介します。
■こんな方におすすめ
・ウェルビーイングを理解しつつも、具体的な実践を描けていない方
・ウェルビーイングという言葉は知っていても、理解できていない方
(資料価値が高く、完璧にまとめられているため、研究者にとっても深く納得がいく内容です)
【目次】
はじめに
第1章 ウェルビーイングと学び
1-1 なぜ今、ウェルビーイングなのか?
1-2 ウェルビーイングとは何か?
1-3 学びをウェルビーイングから捉え直す
column 学校でのウェルビーイングの学びに何が求められるのか
第2章 ウェルビーイング・コンピテンシー
2-1 ウェルビーイングを実現する資質/能力という考え方
2-2 ウェルビーイング・コンピテンシーを把握する基準項目
column アスリートも段階的に獲得する
パフォーマンスに必要なコンピテンシー
第3章 学校教育における
ウェルビーイングの学びの設計論
3-1 ウェルビーイング・コンピテンシーを育む環境と実践
3-2 基礎概念の学び
3-3 ターゲット型/アレンジ型実践による資質/能力の学び
3-4 実践を支えるツール
3-5 ウェルビーイング・コンピテンシーの学びにおける
実践上の留意点
column 地域に開かれたウェルビーイングの学び
CONTENTS
第4章 ウェルビーイングの学びの実践事例
4-1 ターゲット型エクササイズ
4-2 ターゲット型実践事例
4-3 アレンジ型実践事例
4-4 動画付き 道徳科 学習指導案『泣いた赤鬼』
column 教育現場で何が変わったか
創造的な学びのカリキュラムとウェルビーイング
第5章 ウェルビーイングの学びのカリキュラム設計
5-1 カリキュラムの設計指針
5-2 中学校での年間の取り組み実践事例
column ウェルビーイング・コンピテンシーから
大学のカリキュラムを見通す
おわりに
内容説明
子どもたちがウェルビーイングを感じて自ら実現していく資質と能力。
目次
第1章 ウェルビーイングと学び(なぜ今、ウェルビーイングなのか?;ウェルビーイングとは何か?;学びをから捉え直す)
第2章 ウェルビーイング・コンピテンシー(ウェルビーイングを実現する資質/能力という考え方;ウェルビーイング・コンピテンシーを把握する基準項目)
第3章 学校教育におけるウェルビーイングの学びの設計論(ウェルビーイング・コンピテンシーを育む環境と実践;基礎概念の学び;ターゲット型/アレンジ型実践による資質/能力の学び;実践を支えるツール;ウェルビーイング・コンピテンシーの学びにおける実践上の留意点)
第4章 ウェルビーイングの学びの実践事例(ターゲット型エクササイズ;ターゲット型実践事例;アレンジ型実践事例;動画付き道徳科学習指導案『泣いた赤鬼』)
第5章 ウェルビーイングの学びのカリキュラム設計(カリキュラムの設計指針;中学校での年間の取り組み実践事例)
著者等紹介
平真由子[タイラマユコ]
金沢工業大学教職課程 准教授。専門は教育心理学・スポーツ心理学。石川県の公立中学校で社会科教員として勤務し、特別活動主任、道徳教育推進教師、生徒指導主任などを歴任。日教弘教育賞個人部門最優秀賞受賞。教員を続けながら大学院で学び、2020年にスポーツメンタルトレーニング指導士資格を取得。小学生から日本代表選手・コーチまで、メンタル面のコーチングや支援を行う。道徳科教科書編集委員、日本道徳教育学会評議員。学校教育におけるウェルビーイングの実践と研究に取り組む
渡邊淳司[ワタナベジュンジ]
NTT株式会社 社会情報研究所Well‐being研究プロジェクト/コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部感覚共鳴研究グループ 上席特別研究員。専門はウェルビーイングを創成する身体性に基づくコミュニケーション技術・方法論。博士(情報理工学)。ウェルビーイング学会理事。Well‐being Technology展 実行委員長。著書に『情報を生み出す触覚の知性』(化学同人、毎日出版文化賞受賞)など多数
横山実紀[ヨコヤマミキ]
NTT株式会社 社会情報研究所Well‐being研究プロジェクト/コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部感覚共鳴研究グループ 研究員。専門は社会心理学。集団における人々が納得できる合意形成プロセスの設計・評価を研究。博士(人間科学)。2022年3月に北海道大学大学院文学院博士後期課程修了、同年4月から現職にて個人の集団の両方のウェルビーイングに関する研究に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fu_mimi