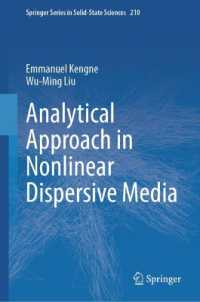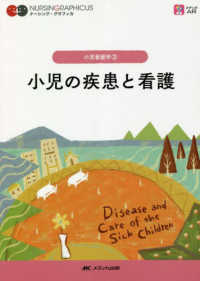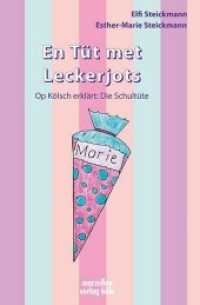内容説明
発問の基礎から応用までわかる!
目次
1 発問とは何か?
2 新規の発問と問い返し発問
3 問題提示場面で使う発問
4 発表・検討場面で使う発問
5 振り返り、統合・発展場面で使う発問
6 思考と表現を深める発問の実践
著者等紹介
盛山〓雄[セイヤマタカオ]
筑波大学附属小学校教諭。横浜国立大学大学院教育学研究科数学教育専攻修了。学習院初等科教諭を経て、現職。全国算数授業研究会常任理事、隔月刊誌『算数授業研究』編集委員、教科書「小学算数」(教育出版)編集委員、志の算数教育研究会(志算研)代表。2011年、「東京理科大学第4回“数学・授業の達人”大賞」最優秀賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
み
17
新規の発問から授業を作るのではなく、子どもの反応や疑問などから出発して問い返し発問を繰り返すことで授業を作っていこうという本。私自身も何度かやったことのある発問があった。途中でストップして全員に「続きはなんだと思う?」ってやつ、以前やったら「どうして最後まで言わせてくれないんですか」って子どもから言われたことがあって、最初に必ず授業のルールを作らなきゃなと反省しました。教室は君だけじゃなくて、全員で学んでく場所なんだよ。2022/03/06
ジーフー
6
問い返しって、要するに子供の発言に返すはつもんみたいなもんでしょ?何て考えていた恥ずかしい時期もありました。いやいや、奥が深い。授業観どころか子供観迄関係するほど、授業の根本的な部分に関わる。 児童の思考を繋げて広め、深めていくために子供達の不完全な発言に対して問いかける。結局は子供達が必死に答えることで真正の学びとなる。 頁数は多くはないが内容が濃かった。2022/01/16
松村 英治
4
発している発問が自分と全然違うことに気付けたし、かなり整理されていて分かりやすかった。GW明けの授業から発問を意識し、自分が使ったものがないものを積極的に使ってみたい。2021/05/01
かるろ
3
教室を温かな空間にすることは授業が起点になるべきだし、問い返しの発問をうまく活用することで狙っていた学級経営に近づけるんじゃないかなって思った。発問を通して子供の心を揺さぶり、子供同士を繋ぎ、思考を深いものにしていけるんじゃないかと思いました。2024/02/16
U-Tchallenge
3
子どもの発言を「問い返し」て学習を深めていくことの大切さはよく聞く。しかし、これは言うは易く行うは難しの典型のように思う。大切ではあるが、「問い返し」ということをまとまった形で学べるものは多くない。よって、本書はとても有益で貴重な一冊に間違いないであろう。問い返し発問について定義され、整理されている。また、具体的な発問例や授業例が示されている。実際の効用を考えやすい内容となっている。この問い返し発問は、算数の授業だけでなく他の教科・領域でも応用することができるだろう。2022/08/01