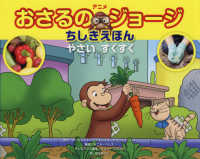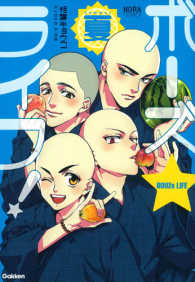感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
107
20世紀を代表する英のSF作家バラードの第一長編。世界中で強風が吹き荒れるようになって、人間の文明は消滅の危機に瀕する。圧倒的な筆力で、さまざまな建物が崩れ去るのを描き出しており、まるでその場に居合わせたような臨場感を感じた。強風の原因は一応科学的に説明されるのだが、そのような科学的な細部よりも、バラードは滅びに向かう人間の社会を執拗に描くことに重点を置いている。建築物が風で薙ぎ倒された都市の様子は、まるでシュールレアリスムの絵のようだ。結末はやや呆気ないが、バラードの筆力が実感できる傑作。2017/04/11
催涙雨
56
この手のディザスターものを読むときにまず思うのが自然の猛威にとって人間の構築する社会的な関係性はまったくもって無意味であるということ。政治家もルンペンも資産家も乳幼児も、区別することなく自然はすべてを薙ぎ払っていく。一方で、こういった危機を前に人間のほうでは立場の強い人間が自分たちのみ生存の特権に浴することのできる環境作りを行い、そのせいで生死という境界線がより一層上下の隔たりを大きくしていく。そして、地球規模の自然の驚異は賢しらな人間の営為が生み出そうとしたこういった格差さえも飲み込んで、すべてを破壊し2019/10/10
Vakira
43
J・G・バーラドさんはP・K・ディック、マイクル・クライトンの様に作品がしばしば映画化される作家だ。クローネンバーグ監督の「クラッシュ」にはぶっ飛んだ思い出。大御所スピルバーグにも「太陽の帝国」が映画化されている。中坊の時によく読んだと思うがあまり内容の記憶がない。当時は面白さが理解できなかったのではと思い、作者の執筆順に読んでみることにした。これは、題名の如く狂風の世界。懐かしい昭和のパニック映画を思わせる。て言うか、書かれたのは1962年の事なので、逆にパニック映画はこの作品を参考にしたのかもしれない2024/01/31
roughfractus02
13
危機が主役の場合、物語は悲劇にも喜劇にもならない。一人の主人公で危機を知ることは不可能なのだ。物語が危機を描くのは、読者の世界に共有されるこの状況を的確に伝える術が他にない場合である。その際複数視点の群像劇が採用される。東風が吹き荒ぶ世界で地上にいる者は壊滅し、地中に潜る者はこの状況が終わるはずだと思い込む。医学博士、情報部の男、潜水艦艦長と視点が切り替わる中で主役である危機が世界を覆う。そしてこのデビュー作を書いた作者は、破滅の風景を見ようとして地面に叩きつけられる女性に後の自作の主人公の原型を見出す。2020/10/28
けいちゃっぷ
8
まだニュー・ウェーブの影響がないのか少ないのか、真っ当と言われれば真っ当なディザスター・ノベル。超科学的な遮蔽物とかを造らずに、あくまでも当時の状況に即した対応。自然の力の前には人類はいかに無力かですね。257ページ2010/10/13
-
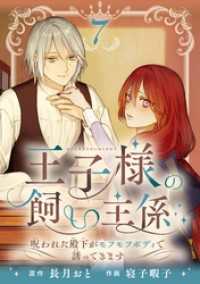
- 電子書籍
- 王子様の飼い主係~呪われた殿下がモフモ…
-

- 和書
- 笑いの品格