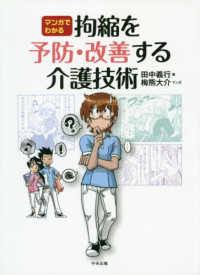出版社内容情報
山路龍天[ヤマジリュウテン]
著・文・その他
松島征[マツシマセイ]
著・文・その他
原田邦夫[ハラダクニオ]
著・文・その他
内容説明
気鋭の仏文学者三人が、「探求」としての読書、「探偵」としての読者という視点に立ち、ミステリーという迷宮に踏み入った「読みの学」の試み。夢野、小栗、中井…「黒い水脈」の魅力を「読む」。日本の探偵小説論の白眉。
目次
謎の物語から物語の謎へ―殺人とは無縁な(はずの)あなたへのプロローグ
第1章 閉じた迷宮と開かれた迷宮―あるいは「探求」のモルフォロジー
第2章 「物語の魔法」の物語―『ドグラ・マグラ』をめぐって
第3章 この世の王国―ミステリーの社会学
第4章 読者への罠―探偵小説のナラトロジー
第5章 意味のみの世界―あるいはレトリックの領域
第6章 器官なき身体=テクスト―探偵小説におけるパロディ現象
第7章 ペダントリーの饗宴―あるいは文学機械としての博識
物語の存在理由―生きのこる(はずの)あなたと私へのエピローグ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
30
ミステリ文学というものの持つ、必然的な構造を分析してみせてくれる論考。そこから文学・物語全般にかかわる語りの構造の分析がスリリング。しかし既読作品なら例に引かれていても気楽に読んでいけるが、未読作品の場合、うっかりネタバレ個所を読んでしまいそうになるので、そこは流し読み。著者が言うようには、読んでしまっても大した影響がないとは思えない。そこがミステリの特性だろう。2016/11/29
拓也 ◆mOrYeBoQbw
21
ミステリー批評・評論本。一般的な評論本と違うのは、特定作品とその周辺を分析する物と違い、「神話、古典、純文学」にミステリー、探偵、スパイ、推理小説の要素を求め、そこらから改めて物語のルーツや構造を分析する手法をとっています。ホメロスやソポクレスに始まり中井英夫『虚無への供物』、シャプリゾ『シンデレラの罠』に至る迷宮文学の歴史です。流石に内容を全て理解するには膨大な作品を網羅する必要がありますが、作品群の中から気になった作品を手に取るのはお勧めですね(・ω・)ノシ2016/07/31
まっつー(たまさか)
4
「犯罪の階級性」「探偵の階級性」については、ロマン・ノワール作家でありミステリ理論家でもあるジャン=パトリック・マンシェットも同じ様なことを述べていましたが、これは文学者や批評家にとっては共通見解なのかな?2024/03/24
hazama
2
86年と言えば大人向けの本を読み始めた頃。まだ鮎川哲也にも松本清張にも久生十蘭にも出会っていなかった。本書の中に流れる空気には余裕が有り、バブル前のなんとなく平穏だったひとときの子供時代を思い出させた。それはそれとして、ここまで実例を挙げて内容に突っ込んだ分析(推理小説としての分析)が一貫してされているのは、とても勉強になる。初出が有斐閣というのも興味深いところだ。それにしても何故96年に創元ライブラリに来た瞬間に読んでいなかったのだろう。20年遅れた。2014/08/10
hobby no book
1
ふだんあまりミステリ系の小説は読まないのだけれど、ギリシャ悲劇をはじめ、推理小説のなかでも古典といったものが扱われていて入りやすかった。2018/09/30
-

- 和書
- 野球検診手帳