- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 日本文学
- > SF小説 アンソロジー
内容説明
探偵小説の第二の波が、日本人が初めて直面した大量死の現実により喚起されたとするなら、綾辻行人を嚆矢とする第三の波は何によって呼び起こされたのか?『本格ミステリの現在』の編纂で日本推理作家協会賞を受賞した著者自らが、綾辻行人、法月綸太郎、我孫子武丸、山口雅也、京極夏彦らによる現代本格ムーヴメントの文学的な意義を確定しようと試みた、秀逸な戦後日本論。
目次
序章 螺旋状の回帰
第1章 世界戦争の小説形式
第2章 戦後探偵小説の盛衰
第3章 「幻影城」の時代
第4章 冒険小説運動の地平
第5章 第三の波の胎動
第6章 大量生と空虚な死
第7章 叙述トリックの探求
第8章 後期クイーン的問題
第9章 第三の波の前線
第10章 構築なき脱構築を超えて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
蛭子戎
2
普段あまり読まないミステリーのブックガイドにと思ったけど読んだことない本ばかりの批評文を読むのは外国語を読むようなものだったしかしそのなかでもまあなんとか楽しく読めたので良かったです。2016/07/03
風見鶏
2
卒論の参考文献。この頃の笠井氏と今の笠井氏は変わらない意見を持っているのだろうか。オウム教団の中核メンバーと同世代であるから~だ、と断じられる綾辻行人氏。東浩紀氏の「何でも世代論になっちゃう」がそのまま当てはまる瑕なのかなと思う。世代論で語れる時代は終わった気がするよ。2014/12/18
縛の場
1
形式化の極限→自壊という本格探偵小説の構造を理論的に説明している。「大量死(=大量生)」論がやや多め。冒険小説の章は未読の作品が多いのでさほど興味を惹かれなかった。『十角館~』『密閉教室』『殺戮にいたる病』『生ける屍の死』『姑獲鳥の夏』『鉄鼠の檻』評論が面白い。コードの徹底化と逸脱、社会的な問題の発見はなるほど、と。探偵小説の無底性、作者の恣意性の問題辺りが最も興味を惹かれた。ただ誤植が多い。『殺戮という病』とか麻耶の第三作『亜』とか。『亜愛一郎』かと一瞬思った……。2016/12/29
おちこち
0
再読。探偵小説の拡散と浸透により社会派と冒険小説に変貌した後、幻影城及び「第三の波」によって再び本格ミステリが多く世にでることになったが、Ⅰで言及されていた時代の作品よりはかなり質が異なっていることが論じられている。「新本格」論として面白い分析が書かれているが、それ以前の「冬の時代」を知るためにもいい論考だと思う。後期クイーン的問題が論じられているが、同時に解決策も書かれていることはもっと触れられてもいいのではないか。2013/02/19
wm_09
0
笠井のミステリ論、新本格編。「大戦間探偵小説」から改めて論を起こしてくれるのでこの本だけでも理論の大枠は充分に分かる。読者として身体で感じたこととは食い違うところもあるが、詳細に亘る分析が熱い。『密閉教室』や『生ける屍の死』についての辺りは圧巻。(稲)2010/06/05
-
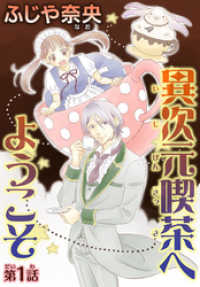
- 電子書籍
- 異次元喫茶へようこそ【分冊版】1 少女…
-
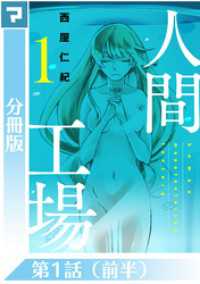
- 電子書籍
- 人間工場【分冊版】第1話(前半)





