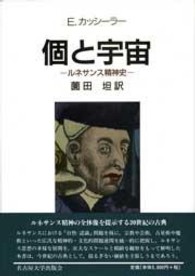内容説明
1970年代から今日まで、常に建築界の第一線を走り続ける安藤忠雄の原点にして、戦後日本の都市型住宅の方向を決定付けた名作「住吉の長屋」。そのすべてを解き明かす。建築家安藤のデビュー作。日本現代住宅史の金字塔となった一軒を徹底分析。
目次
第1章 住吉の長屋―ミクロコスモス(住吉の長屋へ;最初の出会い;「都市ゲリラ住居」の時代;小さな家 ほか)
第2章 「住吉の長屋」とその時代(安藤忠雄「都市ゲリラ住居」;東孝光「町人の優しさと土性骨」;石山修武「怪談 三義人邂逅・一幕一場」;二川幸夫「時代の透き間から」)
資料編(安藤忠雄年表;安藤忠雄建築地図)
著者等紹介
千葉学[チバマナブ]
1960年、東京生まれ。建築家、千葉学建築計画事務所主宰。東京大学大学院准教授。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了の後、株式会社日本設計、ファクターエヌ・アソシエイツ共同主宰、東京大学工学部建築学科安藤研究室助手などを経て、現職。代表作に、「和洋女子佐倉セミナーハウス」(1998年JIA新人賞・グッドデザイン賞)、「黒の家」(2003年日本建築学会作品選奨)、「MESH」(2005年第21回吉岡賞・グッドデザイン賞)、「日本盲導犬総合センター」(2008年日本建築家協会賞ほか受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
287
安藤忠雄の初期の代表作の一つ。この建物は様々な意味において実にユニークである。まずは立地。大阪市住吉区の、文字通り長屋の中央部分である。床面積の大きさはわずかに14.1m×3.3m。この長屋の写真を見るに、かなり奇妙である。両隣のお家の人はクレームをつけなかったのだろうか。周辺の景観に馴染んでいるというよりは、あきらかに異質である。もっとも、今ではすっかり溶け込んでいるのだろうが。次にこの床面積でありながら、中央には中庭が配されている。いわばパティオであろう。雨の日は傘をささないとトイレにも行けない⇒2024/08/27
nbhd
11
大阪にある狭い敷地をコンクリート壁で囲って、1階には中庭があって、2階には渡り廊下があって、3階の屋上部分以外は空がのぞいている、安藤忠雄さんの初期代表作を分析した本。写真を見ながら、うちにもこういう「単なる空間」があったらなぁと、うっとりした。安藤さんの建築に通底するのは、①「建物を覆ったり埋めたりする<地下性>」②「2つの同型造形が並ぶ<双子性>」③「西洋から見ると東洋的で、東洋から見ると西洋的な<二面性>」。このヘヴンリーハウスシリーズは、どれも良い。2017/09/23
インテリ金ちゃん
2
家は、建築家に作り出され、住人と共に成長していく。2013/12/13
ことぶき
1
ファサードの否定。屋根がファサード。それは地下だから。街ではなく、空と関係を持ちたいから。都市の建築ではなく、自然の中の建築だった。ら
mochico
1
一冊まるごと住吉の長屋。安藤さんにも詳しくなれる年表、プロジェクト地図あり:2010年頃購入