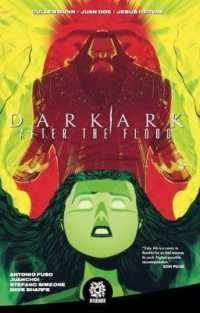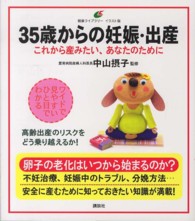出版社内容情報
クジラの祖先が約4?5千万年前に陸上を捨て、なぜ水中での生活を選んだのかを古生物学と分子生物学の世界から紐解く。約4?5千万年前、クジラの祖先が陸上の生活を捨て、なぜ水中での生活を選んだのかを、インド、パキスタン、日本、アラスカなどの世界各地でのフィールドワークを通して古生物学と分子生物学の世界から紐解く。
第1 章 消耗した発掘
化石と戦争 / クジラの耳
第2 章 魚類, 哺乳類, それとも恐竜
コッド岬のトカゲ王 / バシロサウルス科のクジラ類 /
生息地と生活史 / バシロサウルス科と進化
第3 章 足のあるクジラ類
黒白の丘陵 / 歩行するクジラ
第4 章 水泳の技能
シャチとの出会い / 犬かきから魚雷へ /
アンブロケタス科のクジラ類 / 生息地と生活史 /
アンブロケタスと進化
第5 章 山脈が隆起するとき
高いヒマラヤ山脈 / 丘陵と追いはぎ / インドのクジラ類
第6 章 インへの旅路
デリーの立ち往生 / 砂漠のクジラ類 / 150ポンドの頭骨
第7 章 浜辺への旅
外側の砂州 / 化石化した海岸
第8 章 カワウソクジラ
手のないクジラ / レミントノケタス科のクジラ / 骨から獣を作り上げる
第9 章 海洋は砂漠である
法医学的な古生物学 / 飲水と排尿 / 化石化した飲水行動 / アンブロケタスと歩く
第10 章 骨格のパズル
もし殺させるようだと / いくつの骨で骨格を作っているのか? / クジラ類の姉妹群を探す
第11章 カワイルカたち
クジラ類の聴覚 / パキケタス科のクジラ類 / 2001年9月11日
第12 章 クジラ類が世界を征服する
分子SINE / 黒いクジラプロトケトゥス科のクジラ類 / プロトケトゥス科と歴史
第13 章 胚から進化へ
四肢を持つイルカ / 太地町のマリンパーク / 隠れている肢 / 太地における捕鯨
第14 章 クジラ類の前
未亡人の化石 / クジラ類の祖先 / インドヒウス /
第15 章 さらなる道
大きな疑問 / 歯の発生 / 歯としてのひげ
文献
索引
J.G.M“Hans” Thewissen[ジェイジーエムエイチエーエヌエス ティーエイチイーダブリューアイエスエスイーエヌ]
著・文・その他
松本 忠夫[マツモト タダオ]
翻訳
目次
大変だった発掘
魚類、哺乳類、それとも恐竜?
足を持つクジラ類
泳ぎの技法
山脈が隆起したとき
インドでの旅路
浜辺に出かけて
カワウソクジラ
海洋は砂漠である
骨格のパズル
河のイルカたち
クジラ類が世界を征服する
胚から進化学へ
クジラ類以前
これからの課題
著者等紹介
シューウィセン,J.G.M.“ハンス”[シューウィセン,J.G.M.ハンス] [Thewissen,J.G.M.“Hans”]
ノースイーストオハイオ医科大学、解剖学、神経生物学部門教授。クジラ類の研究、特にクジラ類の水中への適応と陸生動物としての起源を研究
松本忠夫[マツモトタダオ]
1943年、東京都生まれ。東京都立大学大学院理学研究科博士課程生物学専攻修了。理学博士。東京都立大学理学部助手。東京大学教育学部助教授。東京大学大学院総合文化研究科教授。放送大学教養学部教授を経て、東京大学名誉教授。放送大学客員教授。専門は動物生態学、社会生物学。とくに熱帯におけるシロアリ類と家族性ゴキブリの社会生態の解明を行なっている。日本生態学会賞、日本生態学会功労賞などを受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。