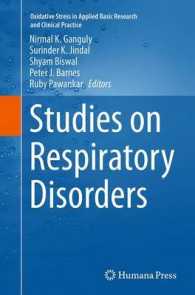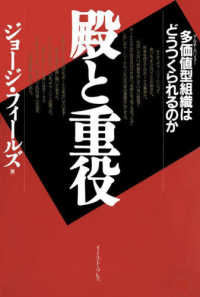内容説明
フーコーのテクストを丹念に追いながら、彼が諸著作・諸論文において展開した「権力‐知」についてのさまざまな批判的分析を、一貫したやり方で、かつ明晰に理解。そこから「批判理論」とでも言えるものを抽出し、その哲学的・思想的な可能性を吟味した。
目次
第1章 『狂気の歴史』と思考の可能性―フーコー・デリダ論争をめぐって
第2章 『言葉と物』における他者の思考について
第3章 『知の考古学』における言表/言説の実定性について
第4章 『知への意志』から『快楽の活用』へ―フーコーの「自己の倫理」の問題系と「権力‐知」批判
第5章 ローマ帝政期における自己への配慮と批判的知の問題―古代倫理をめぐるミシェル・フーコーの比較研究について
第6章 ミシェル・フーコーの批判理論―いわゆる規範的問題をめぐって
第7章 ミシェル・フーコーの比較文明論―境界からの批判的思考の可能性について
著者等紹介
中川久嗣[ナカガワヒサシ]
1961年京都府京都市生まれ。立命館大学文学部卒業。東海大学大学院文学研究科博士課程後期修了。東京理科大学、東海大学非常勤講師などをへて、現在は東海大学文学部ヨーロッパ文明学科教授。博士(文学)。専門はフランス思想、フランス文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
hoshihuman
1
生権力や統治性という中期思想は後景に退いているが、政治的力場としてのフーコーの知の分析論を検討し、比較文明論という視点から光をあてる。考古学や系譜学は一定の時空的まとまりを精査するのであるが、それらは自己言及的なアポリアを抱えている。しかしそのアポリアは、まさに文明の境界-限界へと進むための方法であるために必然的なものである。比較するということは、両者の境界に立つことであるとする筆者は、フーコーの方法を限界に立ち、両者を眺め、それらの限界侵犯する試みであるとする。2014/04/29