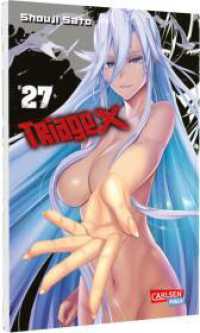内容説明
評論読解テクニックを詳しく解説。また、幅広い主題と分野から精選した評論アンソロジーを収録。
目次
第1部 評論への招待(段落相互の関係;対比;具体と抽象;レトリック―比喩の力)
第2部 (“私”のなかの“世界”―問いかける言葉;芸術の冒険―表現する言葉;科学というスタイル―究める言語;変わる都市・変わる人間―関わる言葉;言葉、この人間的なもの―言葉の言葉;「世界」のなかの「私」―呼びかける言葉;「問い」としての現代―考える言葉;伝統と創造力―時をひらく言葉)
著者等紹介
岩間輝生[イワマテルオ]
國學院大学
太田瑞穂[オオタミズホ]
東京都立日比谷高等学校
坂口浩一[サカグチコウイチ]
東京都立日比谷高等学校
関口隆一[セキグチリュウイチ]
筑波大学附属駒場高等学校(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちくわん
12
2009年3月の本。若い人々(高校生)を対象とした論説文の読解力を高めるための本。取り上げられた28名の評論文は格調高く、意図的に難解に書かれているように感じる。特に良かったのは、原研哉、中沢新一、多和田葉子、中井久夫、鷲田清一、藤田省三、萱野稔人。「問題」は考えなかった。「読書案内」もよし。また、いつか読みたい。2020/02/15
もっち
7
受験生であれば、自習室とかで机の上にさりげなく置いておくだけで周囲を威圧することが出来る本。こんなところで書くことでもないですが、受験国語ではシュミットとアーレントの自由主義の議論をニコ論壇でも見て抑え、仲正昌樹の新書でも軽く読んでおくと、ほとんどの模試の哲学系文章は突破できるので参考程度にどうぞ。2014/03/16
よこしま
5
非常に素晴らしい本です。高校生用とタイトルがつけられていますが、これは大人が評論を勉強するにあたっても充分すぎる作品が勢揃いです。科学技術・言語文化・現代社会などに各プロフェッショナルが鋭い評論をされています。理解して読めたつもりでも、各評論に問題が用意されていて、自分なりに考えて解答を見合わせても、的外ればかり(苦笑)評論の奥深さを実感でき、今までの自分のレビューはどうなんだ?と再認識させられます。大学受験とは関係なく、曲がった世情を生きる中、より広く鋭い視点で各著書を読み、教養を磨いていきたいです。2014/02/27
wattann
4
このシリーズ三部作は必読。2010/12/29
kinako
3
様々な文章構成がパターン別にあってすごくわかりやすい。主題がはっきりみえました。高校の時にであいたかった・・。2010/09/03
-

- 電子書籍
- 拝啓…殺し屋さんと結婚しました【分冊版…
-

- 和書
- キリスト教神学基本用語集