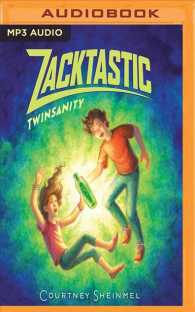内容説明
秩序の内部に無序秩の乱数系をつつみこむ〈秩序=無秩序〉の系が創造を生む。認知科学から数学・経済学、人類学から風俗現象まで、時代の“ゆらぎ”をよみとくパラダイム・マップ。
目次
序章 人間の生命
1 エントロピー
2 コスモス・ノモス・カオス
3 数学のポストモダン
4 不均衡動学と経済
5 古典主義と表現主義
6 アメーバ都市の不確定性音楽
7 社会学と自己組織性
8 無意識の発見
9 中世史ブーム
10 認知科学の時代
11 多様化する言語学
12 サル学と生物学
13 子どもと教育学
14 国家と政治
終章 カオスの弁証法